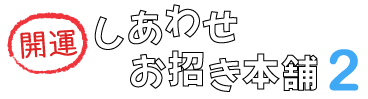恵みの夢

~「夢わたり」一番大切なことを思い出すための45章 より~
……遠い砂漠の町に雨が降った。
その町には、もう何ヶ月も雨が降っていなかった。
雨ごいの祭りが行なわれ、多くの人が、雨の降ることを祈った。
それでも、雨は一滴も降らなかった。
あるとき、一人の旅人がその町を訪れた。旅人も喉の渇きに苦しんでいた。
けれども、誰もその旅人に水を恵んでやれる余裕がなかった。配給の水も尽きかけていたからだ。
旅人を可哀想に思った一人の婦人が、自分の飲み水を半分わけてやった。旅人はとても感謝し、婦人に一粒の種をくれた。
旅人が去ったあと、婦人はその種を地面に埋めた。けれども、雨が降らないので、婦人は自分の飲み水を少しずつ分け与えた。
2週間ほどして、小さなめが出た。婦人は毎日、自分の水を分け与え続けた。
隣の人がそれを見ていて、「そんな無駄なことに、貴重な水を与えるなんて」と非難した。それでも婦人はかまわずに、自分の水を与え続けた。
植物はどんどん大きくなり、婦人の背丈ほどになった。でも、一つの問題が起きた。植物が大きくなった分、婦人が分け与えることのできる水では、もう足りないのだった。すると、いつも婦人を非難していた隣の人が、自分の水を少しわけて、植物に与えてくれた。「どんな花が咲くのか。楽しみになってきたのよ」と、その人は照れくさそうに笑った。
驚いたことに、翌日、植物は二つに増えていた。近所の人がその話を聞き、植物のために自分の水をわけて持ってきてくれた。すると、その翌日には植物がまた増えていた。やがて噂を聞きつけて、町中の人がその植物を見に来た。みんな自分の水を少し持ってきてくれた。そうして、植物はどんどん増えていき、町の広場を埋め尽くすほどになった。みんな、どんな花が咲くのかを楽しみにしていた。
ある朝、植物が花の蕾をつけた。美しい虹色の蕾だった。きっと美しい花が咲くのだろうと、みんなが囁き合った。そして、花が咲いた。ガラスの風鈴のような花だった。虹色の光が花に宿っていた。風が吹くと、その花が可憐な音を立てた。ベルのような音だった。風が吹いて、花が一斉にリロリロを鳴った。まるで花が歌っているかのようだった。
すると突然、天空がにわかに黒くなり、大粒の雨が降ってきた。雨は乾いた大地に染み込み、干上がっていた井戸を満たした。町中が恵の雨の中で、歓喜に沸きたっていた。その植物は、「雨を呼ぶ花」だった。
この世で一番の不幸は、自分がすでに恵まれていることに、気がつかないことである。朝起きたときに、太陽が輝き、新鮮な空気を吸える。顔を洗える水がある。何よりも自分の心臓が動いていて、呼吸をすることができる。眠っている間にそのまま死なずに、目を覚ますことができる。けれども普通は、そんなことにはなかなか喜びを感じない。当たり前だと思っているからだ。
だがもし、重い病気にかかっていたり、事故でベッドから動けないほどの状態になっていたら、当たり前のことが、「当たり前」ではなかったことに気づく。
無くしてしまってから、それがいかに大切だったかに気づくことは多い。自分が「すでに恵まれていた」ことに気づくのは、たいてい失ってからだったりする。
なぜ私たちは、失うまでなかなか気づかないのか?
それは今、目の前にある”苦しみ”や”不都合”で、頭の中がいっぱいになっているからだ。不満が心の中にあるとき、感謝は不在である。自分は不運だ、不幸だと思っている間は「恵み」に気づけない。人がときおり病気になったり、失敗したりするのは、「すでに恵まれている」ことに気づかせるチャンスを何者かが与えているのだ。その何者かは、もう一人の自分だったりする。
不満は、「求める心」から生まれる。何にも期待せず、誰にも求めなければ、不満は生まれない。人はいつもどこかで、何かを求めている。そして、求める心は、与える心をつい忘れる。自分がお腹が空いているときに、他の人も空いていることには気づきにくい。そうして、多くの人は、「まず自分」となってしまう。
けれども、もし、自分の中から人のために「与える心」を出したとき、その人は「自分がすでに与えられていた」恵みに気づくことができる。「呼び水」は、大河を呼ぶ。
気がつけば、不運はなかった、不幸もなかった、すでに自分はたくさん与えられていた。
そんな「恵み」を私たちは、誰もが受けている。