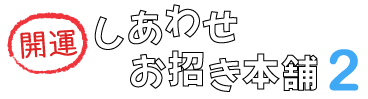今週のお言葉 – 40
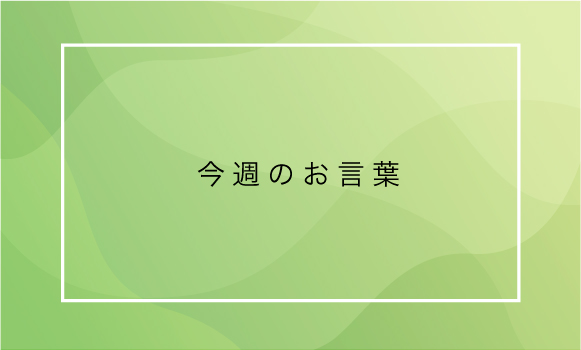
大きく打てば、大きく響き、小さく打てば、小さく響く
前回、僕は、自分がものを書き続けてこれた秘密(幸運)と、そして、それがなかなか世に受け入れられない事に対する自分の力不足を感じるような「告白」をしてしまった。
後で、驚くほど多くの方から、「頑張って!、ちゃんと読んでますから!」とか、「人にも勧めていますよ」というありがたいメールを幾つも頂いた。
その方たちこそ、前回で言った、「応援してくださる力強い味方が現れた」の人たちである。じつは、僕のホームページを訪れてくれる人は、すでに「応援」(それが時に中身に対して批判的な感情を持たれたとしても)者なのだ、と感じている。
せっかく応援してくれる人たちに誤解を生むような書き方だったかもしれないが。例えば、山間に湧き出る「おいしい水」を誰かが発見する。それを分かち飲んでいる人たちがいる。でも、世の中には、その水の存在に気づかない人たちもいる。僕は、どちらかというと、共に分かち合って飲んでくれている人たちの居る側で話している。
それでも、「励まし」のメールは、嬉しかった。ありがたかった。
ある人は、自分が運営する治療所にさりげなく本を置いてくれているとか。訪れる美人(?)の患者さんが読んでくれましたよと教えてくれた。また、ある人は、「人生を変えるヒント3」をやはり病院の待合所に寄贈してくれた。なぜ、三冊目なのか?読めば、続きを読みたくなるだろう? というマーケティング戦略的な読みの深さである。Amazonの書評に、「推薦」の言葉を書き込んでくれている人たちもいる。
気が付けば、無数の応援者がいて、助けてくれている。それは、私たちの誰もが、ある時、感じる瞬間でもある。
自分はたった独りだと泣いていると、そばで見守ってくれる人たちがいる。自分はそれに気づけなかっただけ。何よりも、神さまは、人が孤独の中で嘆いているとき、そっと隣に座って肩を抱きしめてくれている。私たちのすべきことは、「ただ、気づくだけ」である。
読者の方からの「励ましメール」は、共に水を分かち合う仲間の存在を、改めて僕に教えてくれた。ああ、神さま、私の書いてきた姿勢は、無駄ではなかったのですね。
人は弱いから、ときおり、立ち止まったり、振り返ったりして、誰かが居てくれることを確認したくなる。ならば、私も誰かの、その一人になろう、と思う。
けれど、このラセン的構造世界の中で、「宇宙の進化」を垣間見ている私たちは、一つの約束事があることも知っている。
それは、知ったことを、読んだことを、実行して身となり、肉となりに、自分自身ができるかどうか、である。
読むことはやさしい。自分に涙することもできる。その時、確かに人は癒される。だが、一時的にすぎない。「結果」は、いつも「原因」を変えないと、本当には変わらないから。
芹沢光治良さんは、「文学はもの言わぬ神の言葉」だと言われた。でも、「言葉」に触れる、ということは、「どう受け止めるか」を自分に問いかける。書いた人間も、実行を求められる。誰にでもなく、他ならぬ自分自身に。正確には、その人のハイアーセルフに、である。
だから、厳しい。やさしいのに、とても厳しい。その通りにできない自分に逃げ出したくなる。何度も逃げて、他のやさしい道に頼りたくなる。僕もいつもそうだった。
まるで、「完璧なダイエット計画」を書いて壁に貼り、「よし、今日はこれくらいで許しといてやるか。明日から実行しよう」と、書いた自分に安心し、ドンブリ鉢に大盛りのメシを食うように。そして、次の日になると、「うーん、明日から」と一日延ばしにしていく。その連続。
「そのまま、あるがまま」で大丈夫とか、「ちょっとした風水術で、幸運が訪れる」、そんな本の方が、人の胃にも心にも何倍もやさしい、と自分でもそう思う。だから、たくさんの人たちにも受け入れられるのだと。でも、僕にはこれしか書けなかったのだ。きっと、深い自分の中で、求めていたものだから。水を分かち飲む人たちと同じように……。
僕は、自分が挫折しそうになると、ある人の本との出逢いを思い出す。
昔、『人生を変えるヒント』をアメリカに持っていったKさんという女性がいた。その人は、アメリカの厳しいビジネスのまっただ中に身を置きながら、その本をボロボロになるまで何度も読んだという。それこそ、毎日毎日、自分の一日と照らし合わせるように。あるとき、勤めていた会社から、南米の担当を任された。しかし、Kさんにはスペイン語など皆目わからない。彼女は最初、「これは、自分に対するイジメではないのか?」と考えたという。周囲の友人達も気の毒がった。中にはアドヴァイスしてくれる人もいたが、「ヘイ、生きて帰って来たかったら、目の前で開けてくれるミネラルウォーターか、ビールを飲め!」というものだった。(ナンノコッチャ)。
その時、Kさんは、「意味のないことは人生には起こらない。と、本にも書いてあった。きっと、これは自分に与えられた“何か”なんだ。それに、もし、私がイヤだイヤだと思って仕事をしたら、そんな感情で仕事をされた相手は迷惑なだけだ」と、思ったのだと言う。そして、彼女は、現地で「What can I do for you? 私にできることがありますか?」と笑顔で仕事を続けた。
そんな彼女の姿勢は、やがて現地の人たちの心を解きほぐしていった。彼らもまた、言葉もわからない東洋人が来て、何になるんだ!と、不満に思っていたのかもしれなかった。
Kさんの南米での経験は、その後の彼女の人生自体を大きくキャリアアップしてくれた。「どんなことにも、意味があるのだ」と、頭ではなく、心で掴んだのである。
僕は、そのことを手紙で読んだとき、「ああ、この人は大きく鐘を叩いたのだ!」と、思った。「この方の“求める真摯な態度”が、本に隠されているエネルギーの扉を開いたのだ」と。何も悩んでいない人は、「ふうん、いいこと書いてあるけど、当たり前の事よね」と通り過ぎていく。
そうなのだ。同じモノを観ても、人それぞれに受け取り方が違うように、同じ本でも、その人が人生の岐路に立っているのかどうか、あるいは、深く何かを求めているかどうか、で「反響する音」の大きさは変わってくる。そして、それは、本の源流である、神さまだけが知る秘密であり、応えることができるのだ。
「本を生かせる」人は、結局は、「自分自身を」、そして、「他人を」を生かせる人である。誰にでもその能力はある。でも、その時期に、本と出逢えるかどうか、また、出逢っても「気づける」かどうか。それは、神さまにも操作できない(シナイケド)。
以前にも、「私は答えが知りたいのです。でも、ここには、ヒントだけでしょ。答えを教えて」と言われて、返答に困ったこともあった。まさか、「……答えを教えろっ言われても、みんな受け止め方や生きてきた過程が違うから、そのヒントから自分で答えを見つけられる人は、答えを見つけるんだけど……」とまでは言えない。『愛ダス』(日本教文社)を読まれて、「なんだか、説教されてるみたいで……」と、言った人もいる。その時は、さすがに落ち込んじゃったが。
この世界を変えるには、結局は自分自身を「変えて」いくしかない。幸せを求めるのも同じ。
誰にも平等に与えられているのに、誰もが簡単に掴めるはずなのに、自分自身から発している信号に気づかないで、ただ待ち続けている。
たくさんの人に本と出逢ってもらいたい、それは、僕だけでなく、僕を突き動かしてくれた源流の願い。でも、もし、出逢ってもその人が受け止められないのなら……。
自分の力不足を感じるのは、そんな時。だから、より精密に、より正確に、キャッチし続けることが僕のお仕事!と、あきらめないで、頑張ろう、そう思う今日この頃です。