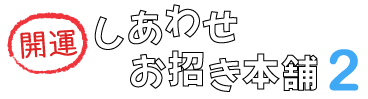今週のお言葉 – 38
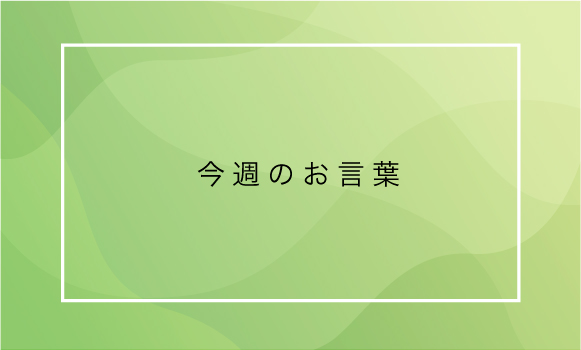
……その森は、閑かに雨を呼吸し、白い霧を吐き出していた
……雨が降っていた。道路に叩きつけるような雨だった。
道に叩きつけられて跳ね返った水の玉が、上から落ちてくる水滴とぶつかり弾けあって、足下を白くけぶるせる、そんな激しい雨だった。
4月半ばだというのに、その雨は冷たく、完全防水のレインウェアーで防護していても、身体の芯まで冷気が染み通ってくるようだった。
地元のホテル「つわんこ」のご主人から、この雨は昼からは止むよと聞いていた。しかし、暗く重い灰色の雲で覆われた空を見ていると、今日一日ずっとこのままなのではないかという想いに捕らわれる。もっとも、雨自体はこの島では珍しくもなんともない。むしろ、それまで続いていた晴天の方が、希有なことなのだという。
一年で365日以上、雨が降ると云われる屋久島。年間雨量は平地で4000mmを越える。東京の約3倍。しかも、山間部では7000mmにもなる。
縄文杉など、世界遺産を一目見ようと訪れても、雨の中をぬかるんだ山道を十時間近くもずぶ濡れになって歩かなければならないことの方が多い島。
そんな屋久島で、初めて体験する雨だった。島を訪れてまだ3日目だが、毎日、抜けるような青空と好天に恵まれていた。
けれども、その恵みの一方で、屋久島の森の最大の特徴である、翠の森の苔は乾燥した岩海苔のように乾ききり、命を枯らして色あせていたのだった。
僕には、屋久島で「見る!」と決めていた二つの場所があった。
その一つが、あの樹齢7200年と云われる縄文杉であり、もう一つが、白谷雲水峡だった。
映画『もののけ姫』の場所として有名になった、深緑の苔むす神秘の森。雨が降ると、森の苔群が光りだすという……。
なあんだ、誰もが行きたがる「お約束の観光所」じゃない、と冷やかすなかれ。
雨降り島の屋久島では、雨天に映えるという白谷雲水峡でさえ、増水のために入れないこともあるのだ。
縄文杉には、晴れた日に逢いに行きたい! 白谷雲水峡に行く時には、ちょっと雨が降ってくれればいいな! そんな贅沢で自分勝手な旅行プランで臨んだ屋久島の旅だった。さらに、ワガママな想いがもう一つ。それは、縄文杉に逢いに行く前に、白谷雲水峡を訪れておきたい。クライマックスは、屋久島の森のエネルギーの「洗礼」を受け、身体一杯に満たした後で体験したい。だから、ねっ、神さま、お願い。白谷に行く時には、雨にして。でも、縄文杉の時には、晴れさせて! (日照りが続いて、雨請いのために「生け贄」まで出して苦しんだ古代メキシコの人達から見れば、とんでもない事をぬかす罰当たりな奴、である)
そして、その朝、僕は、恵みの雨の中を「白谷雲水峡」に出かけたのだった。
僕が泊まっていた安房の地から、宮之浦までバスで30分。そこから、白谷雲水峡行きのバスに乗り換えて約30分かかる。
朝7時37分のバスに乗れば、白谷雲水峡には、9時前には付く。
バス亭には、宮之浦高校に通う高校生達が傘をさしてバスを待っていた。バス亭の前のお弁当屋さんで、竹の皮に包まれたおにぎり弁当(海苔で巻いたおにぎり二つ、焼き魚一切れ、たまご焼き一切れ、鳥の唐揚げ一個とタクアン二切れで、360円)を買う。これが、今日一日の食糧となる。
濃紺のブレザーに白ズボンの学生達の横で、僕はアマガエルさんのような緑色のレインウェアの上下に黒い帽子、防水機能の優れた茶系と黒のトレッキングシューズ、さらに、足首からの雨水の浸入を防ぐブルーの防水カバー。背中には、濃いグリーンのリュックサック。中の荷持つを濡らさないためのオレンジ色のリュックカバー(宿屋のご主人に借りた)と、色彩感覚のあまりにもバラバラな感じが、ちょっと嬉しい。
やがてバスがやってきた。
バスは「日常」の高校生達と「非日常」の観光客である僕を乗せて、雨の中を走り出す。遠くに見える山々に朝もやがうっすらとかかっていた。
白谷雲水峡の入り口には、すでに多くの観光客が集まっていた。受付で、どこから来たか、とだけ聞かれる。遭難対策らしい。
「さあ、もののけ姫の森に行くぞ!」と、石で舗装された案内路に踏み出した。静かな興奮が身体を包む。未知のものに逢いに行く感覚。
雨は、先ほどよりは小降りになっていたが、それでも、視界を狭くするだけの水滴は舞っていた。
白谷広場から「飛流おとし」と呼ばれる滝を抜け、「さつき吊橋」を渡ると、そこから先は、原始の森が待っていた。
地面に黒いヘビのようにのたうつ露出した屋久杉の根っこと緑色の苔で化粧された石だらけの山道が続く。
僕は、昨日までの屋久島と、明らかに違った気配を感じていた。
森全体の「生気」が強くなっているのだ。
雨の恵みを享受して、森を取り巻いている苔たちが、ようやく「ひと息付いた」という感じだろうか。
草の汁を何百倍にも濃くして、そこに杉独特のすうっと鼻に通る香りやその他のナラやクヌギ、ツバキなどの常緑広樹の椿油のような香り、下生えの羊歯や苔から発する秘密めいた匂い、それらを巨大な空気の鍋の中でゆっくりとかきまぜ、ブレンドしたような、森の匂い。
森の体臭とでも言うべき、濃く鮮やかな緑の匂いが、あたり一面に満ち満ちていた。
そのせいか、冷たいはずの雨が、森の体温を感じて、温かな「Warm Rain」になっていた。
倒れた屋久杉に密生したシダ類や幾種類もの苔が、雨露にしっとりと身体を濡らし、芳香を放っている。
苔は、実はとても良い匂いがするのだ。ときおり、カビくさいような匂いがするのは、腐葉土のように、土と一緒になって微生物によって発酵して分解しつつある時の匂いである。苔自体は、近づいて嗅ぐと、日だまりで乾かした海苔のような香りがする。
……雨の中で、深い緑色の苔が光っていた。目には見えない白いオーラを放っていた。
苔が、閑かに雨を呼吸して、白い霧を吐き出している。その白いオーラが、森全体を包み込んでいるかのようだった。
「世界は、ただ霧の中に」昔、何かの本で読んだ、そんな言葉が浮かんだ。
僕は、その白い森の中で、たまらなく異邦人だった。
『わら一本の革命』(春秋社)を書かれた自然農法家の福岡正信さんは、「森が、雨を呼ぶのだ」と言われた。
砂漠を緑化するには、そこに森を育てれば良いのだと。雨は、森が呼んでくれるからと。
屋久島は、ほとんどが花崗岩で出来た島である。土壌が薄く、栄養になる肥料も少ない。森林が生育するには適さない。だが、屋久島の森の樹は、どれも異様なまでに長寿で巨大化している。巨大な岩の上に根を貼り付かせたように育っている屋久杉。岩全体を、タコが獲物をその吸盤のある足で包み込むように、杉の根がしっかりと抱きしめている。根が岩の中に入り込んでいるのか、それとも、岩が根と同化しているのか、そんな不思議な光景を目にする。
足りないはずの栄養は、じつは塩などのミネラルを含んだ雨がもたらすのだという。
屋久島の森は、原始の地球が持っていた「力」をそのまま温存しているようだ。だから、この島だけ、異常なまでに雨を呼ぶのか、と思う。
森の樹々の持つ磁場が、その地の重力場・グラビィトロンフィールドに干渉して、その空間だけ磁力を強くする。すると、森の上空の大気に「窪み」のような異相が生じる。その引力に引かれて、水素と酸素が集まってくる。重力の磁場はまた、空中の電気(電気の正体は生体磁気)にも働きかけ、強いイオンを発生させる。そして、酸素と水素の原子がぶつかりあって美しい水の分子が生まれ、雲を形成する。雲は、なおも引き続ける磁場で密度を濃くし、やがて雨雲に成長していく。
こうして、森に雨が降るのだ。
……と、森に秘密をそっと教えてもらった。
余談だが、屋久島の樹々が、成長が遅く、巨大化するのは、「微食」のせいのように思う。食べるモノが少なく、栄養を摂れないために、樹が持つ生命力が強く引き出され、ゆっくりと成長していくから、巨大で長寿になるのではないか? と、思うのだ。やはり、世界は皆、「微食」が正しい?
白谷雲水峡の原始の森に踏み入ってから、2時間以上が経っていた。
お昼をまわっていたが、雨はまだ降っていた。それでも、時折、雨雲が切れて、その灰色の切れ間から太陽が顔を覗かせたりするから、宿のご主人の予想通り、午後からは雨が止むのだろう。
レインウェアの下は、すっかり汗をかいていた。ウェット&ドライのTシャツが、蒸気のように、身体からの汗を放出する。雨の森の胎内で、僕自身から出た蒸気と森の生気が混じり合って、人間でもない、森でもない、一つの空間を生み出していた。僕は、きっと森に棲むみつく両生類のように、森の呼吸と同調していたにちがいない。
人が腰をかがめて通り抜けられるような、二本の杉が途中でくっついて成長した「くぐり杉」を抜け、休憩所である白谷小屋を過ぎ、なおも森の深奥に入っていった。
ここからは、いよいよ「もののけ姫の森」である。と、言っても、標識のようなものがあるわけではない。宮崎駿さんの映画『もののけ姫』が、屋久島の森のイメージから生まれた事に由来して、誰言うともなく「もののけ姫の森」と呼ぶようになったのだという。
もっとも、すでに苔に覆われた世界に浸かり込んでいる僕たちには、「境目」などわからない。森がより原始的なジャングル的迷宮を見せている感じか。
確かに、全体的に苔による森への浸食が大きくなっている気はする。目の前に見える樹も石も道も苔に覆われている。
視界がほとんど深緑一色になった気分。
そのとき、僕は、緑深い海底にいた。
僕は、もう自分が森の空気を呼吸しているのか、それとも、苔の吐き出すオーラを呼吸しているのか、わからなくなっていた。
どこかで、あの「シシ神」のような存在が、不用意に森に侵入した人間をじっと見つめているような気がした。
かつて屋久島の森は、人間が勝手に入ってはいけない森だったという。
屋久島で生まれ育ったという、宿屋「つわんこ」のご主人はそう言う。
「神さまの森」なのだと。今でも、島の長老達は、森の中に観光客が入っていくことを快く思っていないとか。
毎年、屋久島では人が遭難している。不注意から起こったり、山をなめた結果の事故もあるが、「神隠し」としか思えない事件もあるのだという。
島にも山にも詳しいはずの地元の人が、山の中で何日も迷ってしまう事もあるらしい。
救助された後で調べてみると、本人がいつも通い慣れていた山道だったりする。では、彷徨っている間、その人を支配していたのは何だろう?
昔、屋久杉を切るときは、前の晩に斧を木に立てかけたという。
翌朝、斧が倒れていたら、その木には「神さま」が宿っているから、切ってはいけない。斧がそのままだったら、その木は切ってもかまわない。
……人間と森との不可侵の条約。人間は忘れても、森はきっとそれを忘れてはいない。
世界遺産に登録されたために、毎年、多くの人が屋久島の森を訪れる。注意をしていても、人は木の根っこを踏んでしまう。苔を靴底で削り取ってしまう。
何百、何千、何万という人の悪気のない足が、森を踏んでは傷つけていく。
苔は、何年もかかって地に根付く。削られても、一日では再生しない。
『もののけ姫』の精霊たちが滅びていったように、いつか、屋久島の森も神秘の光を失うのだろうか。
日本の森の多くは、「鎮守の森」として守られてきた。神さまの領域だからと宅地開発も避けられてきた。
そうして、日本人は森を巧みに守ってきたのだ。
マヤの人たちの住処(すみか)だったアマゾンの森は、開発のために日々失われている。
「人が入ってはいけない森」、自分が行って、さんざん感動しておきながら言うのも勝手だが、そんな森が日本にも世界にも残ってほしいと思う。