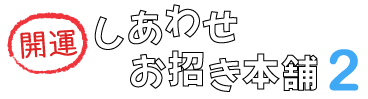今週のお言葉 – 34
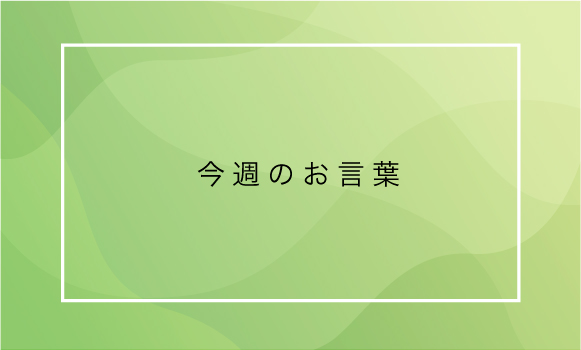
二度と来ない 今日というこの日 この一日を百日のように生きたい
星野富弘 花の詩画集『速さのちがう時計』(偕成社)
無力感にさいなまれた日々が、まだ続く。
昨年末に起きたインド洋スマトラ沖の大地震による大津波は、30万人もの犠牲者を出しつつあるという。
私は、あの頃から、2週間あまりもカゼで寝込んだ。文字通り、寝正月だった。
ニュースを見て震え、どんどん増えていく被害者の数に呆然としていた。
あまりの被害の大きさに、祈りが消えてしまいそうだった。
その前では、ただ無力さだけを味わった。
私の知り合いを含め、仕事で関わってきた人たちに、身内や友人の安否を尋ねることしかできなかった。
知り合いの一人は、その時、南インドにいたが、ホテルで眠っていて助かった。現地から「なんとか大丈夫」というメールが届いた。
また、もう一人の知り合いは、休暇をダイビングで過ごそうとしたが、プーケットへの飛行機やホテルが取れず、バリ島に変更したために助かったという。
けれど、私の知らないたくさんの人が亡くなった。
誰も予知できた人も、防げた人もいなかった。
地震学者がテレビで原因を詳しく説明しても、虚しく聞こえるだけだった。
聖書には、「その日が来ることを天使さえも知らない」と言うが、その日が来れば、こういう悲しみが何度も世界を覆うことになるのか、と実感した。
ネイテイブ・アメリカンなど世界の先住民たちは、来たるべき地球の変動を「浄化の期間」だと言う。
今までの人間の「奢り」によって痛んだ地球が、再生の時を迎えるのだと。そして、この期間が過ぎれば、人間が本当の人間らしく暮らせる世界が来るのだと。
けれど、お腹を壊した時の浄化とは比べモノにならない。
「悲しみ」が大きすぎる。
もっと他に、「道」はないものか?
津波の被害の報道は日々少なくなっていく。
誰も悲惨なニュースから目を背けたいのだろう。
けれども、被害にあった人の家族や友人は、悲しみの中に取り残されている。
人智学の提唱者、ルドルフ・シュタイナーは、災害などで亡くなる方は、次の地球の準備のために早く逝くのだと言う。
そのことを信じたいと強く思う。
でも、災害による死者を見ると、おごそかな死を感じにくい。人間の尊厳を失うようで、心が痛い。
家族の悲しみが伝わってくるように思う。
そして、天の悲しみを想う。
今、私たちにできること。
私たちが為すべきこと。
この一日を無為に過ごすことなく、大切に生きていきたい。
自分の生に「一期一会」で。