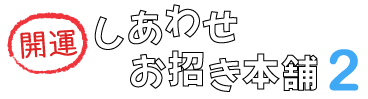今週のお言葉 – 31
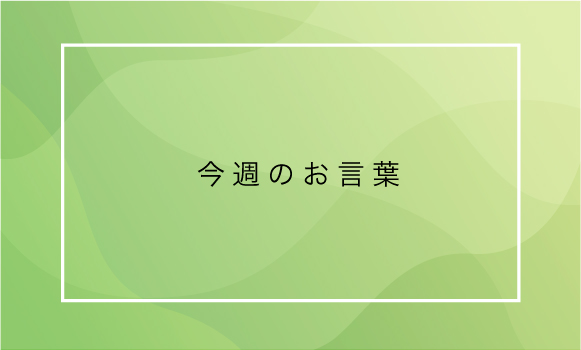
信仰が始まると心配がなくなり、心配が始まると信仰がなくなる
木村清松牧師
この言葉は、私の中にとても深く入ってくる。
ともすれば、「祈り」が習慣的なものになってしまっていたりする信仰心の足りない私は、「祈りもまた一期一会」なのだと再認識させられた。
……そうなのだ。人は、何か悩んでいることがあったり、心配事や不安の中にいるとき、その解決を求めて、真摯な態度になる。
その時の「祈り」は、せっぱ詰まっていて、とても真剣である。
けれど、過ぎ去った嵐のように、悩み事や心配事が無くなってしまったりすると、その「祈り」は、どこか、ひたむきさに欠けている。「喉元過ぎれば……」である。
大水を前にして祈った瞬間だけが本物の「祈り」だった老婆の話(「人生を変えるヒント2」の93番)と変わらない。
生長の家の創立者、谷口雅春さんは、聖経『甘露の法雨』の中で、こう示されている。「……物が殖えたときに信仰を高め、物が減ったときに信仰を失い、身体が健康になったときに神を讃え、家族の誰かに病気が起こったと云っては信仰を失うがごときは、神を信じているのではなく、物を信じているのである……」
私たちは、物の移り変わりに心を捕らえられる。
自分や身内の者が病気になれば、治して欲しいと願う。
良くなると喜び、回復がはかばかしくないと暗く沈む。
まさに一喜一憂してしまう存在である。
木村清松牧師の云われた意味は、物の御利益の上に建てられた揺れる信仰ではなく、「信仰」の中にまるっと自分を放り投げてしまっているかどうかという次元の問いかけである。
多くの聖人と呼ばれた人たちの為した、「献体」である。
神さまの中に自分を委ねきっている状態こそ、「信仰」と言うのだ。それは、大宇宙とつながり、その胎内にいる安住感である。
逆説的に言えば、私たち人間は、神さまとつながっていない時は、常に「不安」の中に身を放り投げてしまっていて、そのことに自分で気づいていないのである。
翠ケ丘教会の井殿準牧師は、木村牧師の言葉を受けて、「我々が自らの強さに頼っているかぎり、我々の中から心配は無くならない」と、説かれた。
自我による「祈り」から、魂の声の「祈り」へ。
「いつも喜んでいなさい」
……あの方の光が響いてくる。
★H町の翠ヶ丘教会は、私がときおり日曜礼拝に参加させてもらっている(じつは聖歌隊にも入っていたりして……)教会です。