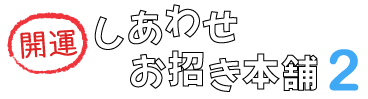今週のお言葉 – 65

家庭の味と、家庭的な味
先日、Y駅の近くの「欧風料理屋Bistro」と、カンバンを掲げている所に入った。
たまには、洋食もいいなと思ったからだ。
ただし、僕はお肉は食べないから、エビ入りコロッケとか、豆と野菜のスープとか、ポモドーロ(トマト味)のスパゲッティとかを頼んでみた。
メニューには、“欧風家庭料理”と謳ってある。
「うーむ、これは期待できるかも知れぬな」
こざっぱりとした店内には、家族連れが二組と恋人同士らしいアベックが三組ほど入っていて、すでに食事をしていた。
中年の夫婦が二人で切り盛りしている店らしく、奥さんが注文を聞きに来て、ご主人が厨房で独りで料理を作るらしい。
色の浅黒い、ヒゲの生えたスーパーマリオのような顔が、イタリアンしていた(そうか?)。
琥珀色のビールを楽しんでいると、目の前をじゅうじゅうと音をさせながら、肉の乗った鉄板が運ばれていく。まだ若い、十代の女の子のテーブルにそれが届けられる。
「おいしそー」と顔がほころんでいる。
あちらのテーブルでは、おじいちゃんが皆に平等に分けられたはずのスパゲッティをもの凄い早さで平らげて、嫁から新しいのをもらっている。
日曜日の午後の微笑ましくなるような光景。
そして、待つこと20分。とうとう僕のテーブルにも料理が運ばれてきた。
エビ入りコロッケとグリーンサラダは、まあまあの味だった。
かかっているデミグラスソースが甘辛くて美味だった。
お豆と野菜のスープは、ポタージュで薄塩味だった。
この分だと、まあいいかな、と期待していたら、メインに頼んだナスのポモドーロスパゲッティが到着した。
トマトの酸味がつんと香った。
服を汚さないように、ナプキンを喉まで引き上げて、フォークで麺をからめ取った。
一口ほおばる。
んっ?
僕の中の何かが沈黙した。
アルデンテでもない、麺は伸びている。
味もケチャプをそのままかけてあるような……。
気のせいか、オリーブオイルもギトギトしている。
ナスビは芯まで火が通っていないのでは? と。
「こ、これは!」
僕は唸った。
“家庭的な味” ではなく、“家庭の味” なのである。
そのとき、僕の脳裏に忌まわしい過去の記憶が蘇った。
あれは、忘れもしない、今から15年も前の事だった。
仕事の関係で那須塩原に寄ったものの、帰りが遅くなり、予約していた電車に間に合わなかった。
仕方なく、宿を探してもらったのだが、あいにくと休日前でどこも満室だった。
一軒だけ、民宿みたいな所があると地元の人が紹介してくれた。
地図を頼りに訪ねてみると、普通の建て売り住宅のような家だった。しかも古い。けれども、表札の横に確かに「民宿」とある。
まあ、泊まれて、食事があればいいや、と思ったので、呼び鈴を鳴らした。
中から、エプロンをしたおばさんが出てきた。どこにもいる主婦の感じである。
「はいぃ? ああ、連絡もらいました。どうぞぉ」と、愛想はいい。
普通の家の玄関で靴を脱いで、スリッパに履き替え、居間と台所を通って、二階の客室に案内された。すでに、布団が敷いてあった。
浴衣に着替えていたら、さきほどの女将さんが来て、
「お風呂、先に入ってもらえますかあ? 子どもがもう寝ますので」
そう言われて、お風呂に入ると、タイルのお風呂で、子どものオモチャのアヒルさんとかが置いてあった。
親戚の家に泊まりに来たような感覚だった。
それでも、さっぱりして出てくると小さなお膳用テーブルに僕のために用意された食事が載っていた。
「急やったんで、なんにもありませんけど……」
と、女将さんは言う。
そこには、白いご飯とおみそ汁とコロッケ二つとキャベツの盛られたお皿があった。
そして、僕の隣では、四角いテーブルがあって、そこで、家族四人(父親、母親、子ども二人)が同じ食事をして、テレビを見ているのだ。
「あっ、ご飯お代わりやったら、言うてくださいね」
と、親父が挨拶してくれた。会社勤めのサラリーマンなのだろう。
「はあ、どうも……」
後の言葉が続かず、僕はもそもそと食事を始めた。
すると、その家の小学生らしい男の子が、
「お母ちゃん、なんで僕のコロッケ一つなん?」と母親に文句を言った。
そっと、隣のテーブルを見た。
確かに、子どもと父親のコロッケが一つずつになっている。合わせると僕の二個になる。
僕は、早めに食事を済ませて、二階に上がったのだった。
その話を何年かたって友人に話したら、
「それは、家庭的な民宿やのうて、民宿みたいな家やな」と言った。
長い余談になってしまった。
つまり、僕の言いたいのは、「家庭的な味」と「家庭の味」とでは、ものすごく違う! ということなのだ。
家庭の味は、すなわち家の味である。それをそのままお店に出す人はいない。
食べに来る人たちは、プロの技にお金を払うからだ。
家庭的に見える、でも、そこには、プロの技術が光っている。そんな「家庭的」を求めているのだ。
そう。僕は、プロの技が見たい、と思う。職人の仕事に憧れる。
でないと、素人がプロになっていく醍醐味がないじゃないか、とそう思うのだ。
そして、そのことは、「本物」と置き換えられるように思う。
「本物に見える」ニセモノはもういらない。
目だたなくてもいいから、本物に出逢いたい。
そして、自分も本物に近づいていきたい、と。