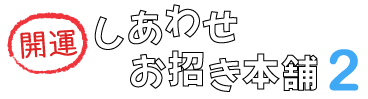お告げ – 番外編4
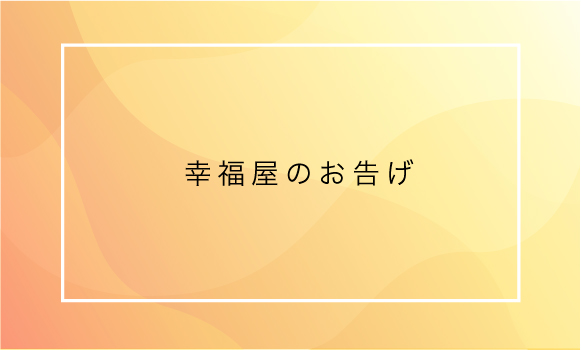
アース・ヒーリング
「神は鉱物の中に眠っている。しかし植物の中に神は目覚める。
そして、神は動物の中に歩き、動き、人間の中で考える」
サンスクリットの碑文より
イルカ 青の惑星の癒しの使者
「人生をやり直せるなら、こんなスタートがいい!」―そんな午後だった。
眠りを誘うような波が船底の木に当たっては、船の抵抗で押し戻されていく。その微かな振動が、デッキに寝そべっているぼくの身体に見えない波のようなものを伝えてきた。
「ゆらぎ」とは、本来こういう揺れを言うのかもしれなかった。赤ちゃんが揺りかごで快適に眠る理想的な揺れも同じだという。羊水の中の記憶が甦るのかもしれない。
フロリダの南端、珊瑚礁の島々が連なるキーズの海を、サンセットクルージングの船がすべっていく。船は、緑鉱石(エメラルド)でできた透明な水の上にいた。光が水底に反射して、エメラルド色に海の水が染まっているのである。水深は五メートルもあっただろうか? 驚くほどの透明度で水底の丸くなったサンゴの石がはっきりと見て取れた。このあたりは、珊瑚礁の特徴か、浅い海が続いているらしい。美しい虹色の熱帯魚がヨットの下を素早く駆け抜けていった。
遠くに、蜂蜜のような太陽が大きく水平線に傾きかけていた。太陽の傾きかけたあたりの海は、蜃気楼のように金色に熔けていた。
「あれは涅槃の光だよ」と教えられたら、吸い込まれてもかまわないと思える美しさだった。
さきほどから船長と助手である奥さんが、ヨットに乗り合わせているぼくたちにシャンパンを勧めてくれていた。冷えたシャンパンが、太陽の照り返しで焼けた喉を癒してくれた。ヨットは風を上手にさばき、波の上というより、空中に浮かんでいるようだった。ときおり、波紋のような揺れを感じる程度である。船長が赤く塩焼けした鼻を指先で弾きながら、「こんなに静かな海は珍しいよ」と話してくれた。
「静かな海」とは月のクレーターに付けられた名称だが、この安らいだ気持ちは、たとえようがなかった。まるでメロンソーダの海の上を水晶で作られたカヌーがゆっくりと滑っていく感じだった。むろん、何も音がないわけではない。マストに張られた帆が風を受ける音、舵が曲がるときのギィという重い響き。そして、キャビンに取り付けられたスピーカーからは、エンヤの「オリノコ・フロウ」が流れていた。エンヤの透明な歌声がこれほどピタリとくる情景はなかった。できすぎた感じだった。
エンヤの曲を聞いて、不思議な郷愁にかられる人は多いという。それは、ビートルズを聞かずに育ったという彼女の環境に関係している。彼女は語り部(フィリー)であった祖母からケルトの古い神話や民話を聞いて育ったという。
ケルトとは、古代アイルランド人の祖先であり、紀元前二〇〇〇年前には中部ヨーロッパにいた先住民である。その起源は、『旧約聖書』に語られる以前に遡る。かつては、ヨーロッパからアジアまで広く分布していたが、ローマ人やゲルマン人、アラブ人に追われて、ヨーロッパの西へと流れていった。
現在は、アイルランド、スコットランド高地、ウェールズ地方、コーンウォールとマン島、そして、フランスに一部残るだけとなった。ケルトは、ドルイドと呼ばれる男性ばかりの宗教組織によって導かれた自然崇拝の民だった。世界の多くの先住民がそうであるように、万物の中に精霊が宿っていると信じていた。エンヤの歌に、欧米人に多い自己主張が感じられないのは、失われた民族の魂を彼女が伝えているためなのかもしれない。
ケルトのシンボルは、三つの渦状紋である。その渦巻きは、クリチャンに改宗させられたアイルランドの人たちの十字架の中に今も生き残っている。三つの紋とは、キリスト教で言う「天と地と精霊」の三位一体と同じである。天は神、地は人間、そして、精霊とは天と地をつなぐスピリットのことである。解釈によっては、人間の精神と肉体と霊魂の三位一体を意味する。中国には太極を表すまが玉が合わさった二つ巴の「陰陽」のシンボルがある。陰陽の二つの勾玉とその境界線で三位一体である。まが玉の曲線は、「流れる」ことを意味する。万物の本質が「変化」にあることを示唆している。ケルトの渦状紋も左から右への陰陽の流れを表している。まが玉を守護のシンボルとした日本の神道にもその流れは伝わっている。和歌山県の熊野速玉大社と東京の神田明神がケルトとまったく同じ三つの渦状紋である。
先住民の歴史を辿っていくと、世界が、現在知られている歴史よりも遥かに古く多くの秘密を持っていたことに気づくだろう。
風が少し変化したようだった。先ほどよりは、帆を張らませるカーブが大きくなっていた。太陽はいよいよ半身を海の中にゆだねていた。水面に浮かぶ金色の道が太陽から伸びている。その道に乗れば海の上を歩けるのでは、という気にさせる。船長の奥さんがもう一杯どうか? とシャンパンのビンで手招きした。こんな極楽の世界に連れていってもらって、よく冷えたシャンパンが飲み放題で、一人45ドルは安かった。
ふと、思った。今、世界で戦争をしている人たちが、家族や恋人とこういう平和な時間を持つことができるなら、この瞬間に人も地球もどれほど癒されるだろうと。人を戦争から遠ざける一番の方法は、戦争反対の闘争をすることではない。人に平和で安らかな時間を与えることである。それは、旅人と太陽と北風の関係に似ている。
じつは、キーズを訪れた目的は、グラッシー・キーにある「ドルフィン・リサーチ・センター」の見学のためだった。そこでイルカと一緒に、身体や精神に障害を持つ子どものヒーリング・セッションを行なっていることを聞いたからである。
滞在していたホテルから車で一〇分ほどの所にドルフィン・リサーチ・センターは建っていた。研究所といっても、白亜の建物が並んでいるのではなく、プレハブの簡単な建物だった。この研究所は、非営利の施設として運営され、水族館で病気になったり、外洋で捕獲されて傷ついたイルカを介護して海に戻す仕事をしている。施設には、ここで生まれたイルカ(テレビでお馴染みになったフリッパーの子どもターシィもいる)を含め、自然の中で飼っている約十五頭のイルカがいるという。
スタッフは全員がボランティアで、Tシャツにジーンズのショートパンツ姿というラフなスタイルだった。生物学者のデビッド・ネイサンソン博士も、同じ姿に頭に魚のぬいぐるみのついた帽子をかぶって座っていた。日本からスーツを持ってきて訪ねてきたのがちょっとこっけいに思えてしまった。これが日本だったらどうだろう。外国から予約を入れて見学に来た人をTシャツ姿では迎えないだろう。国や習慣の違いもあるが、イルカという水の精霊と一緒に暮らしている、何も飾りたてる必要のない人たちと文明のフィールドの枠の中にいる私たちとの違いのような気がした。
その日は、アメリカのABCテレビが撮影に来ている日だった。テレビ局が連れてきた子どもたちは三人いた。マーク(仮名)という一三歳の少年は、半年前の交通事故で下半身不随になり、そのときもこのリサーチ・センターでイルカから治療を受けたという。その後、治療のかいあって少しだが歩けるようになったらしい。だが、そのことはまだ博士には知らせていなかった。二人目の少年はアラン(仮名)八歳。生後半年で高熱のために全盲となり、全身小児マヒにかかっていた。そして、最後の一人が七歳の女の子エレン(仮名)だった。エレンは表面的には健康に見えた。だが、強度の自閉症で感情を表さないという。
撮影は両親の承諾の下に行なわれているようだった。自分の子どもがそれで癒されるなら、また、子どもと同じような病気で苦しんでいる人たちの助けとなるならと、アラン少年の母親が語っていた。
博士は、エレンから始めた。彼女をそっと抱き抱えて自らプール(海の入り江の一角を低い柵で仕切ったもの)の中に入っていった。そして、 待った。すると、二頭のイルカが現れた。イルカたちは、ゆっくりと博士とエレンの周りを泳ぎ始めた。エレンが彼らを恐れているのを敏感に察知しているようだった。無理もない。生まれて初めてイルカを目の当たりにしたら、その大きさに驚いてしまう。エレンの博士にしがみついている手が強ばっていた。緊張して力が入っているのだろう。岸辺では、母親が心配そうに見ている。マーク少年もようすをじっと見ていた。アラン少年は見えないけれども気配で何かが起こっていることはわかるらしく、落ち着かないようすだった。
そのうち、一頭がすうっと近づいてエレンに鼻をすり寄せた。博士はエレンの手を取って、何かを語りかけている。が、小声なのでこちらまでは聞こえてこない。どうやら、「触ってごらん」と言っているようだった。それでもエレンは怖がって手を出そうとはしない。すると、もう一頭がエレンのそばで優しく鳴いた。
クルルルルル・・・
エレンはびくっとしたが、その「びくっ」は、先ほどまでの感情とは変化しているようだった。彼らが自分を脅かす存在ではないらしいことを本能で知ったようだった。最初の一頭がまた鼻を近づけてきた。今度は博士はエレンの手を無理に取ろうとはしなかった。エレンの好きにさせておいた。エレンはじっとイルカを見ていた。もう一頭がまた短く鳴いた。「触ってごらんよ」とせかしているような声だった。エレンはそっと手を伸ばした。そこにイルカが自分から鼻を伸ばしてきた。エレンは思わず手を引っ込めた。だが、今度はその顔に恐れの感情は浮かばなかった。博士は辛抱強く待っていた。博士は知っていたのだ。人間の自分がこの少女に今してあげられることは、待つことだけであることを。
エレンはそれからも自分からは手を出そうとはしなかった。それでも、イルカに触った手をじっと見つめていた。イルカたちは、今日はここまでというように去っていった。午前中のセッションはそれで終わった。ぼくは聞きたいことが山ほどあった。だが、母親はもっと知りたかっただろう。それでも彼女は黙っていた。ぼくも何も聞かないことにした。
午後は、アランの番だった。マークは明日だという。アランの場合は目が見えない上にマヒした身体をどうやって支えるかの相談がなされた。結局、車イスで行けるところまで行って、母親とスタッフがアランを抱き抱え、プールの中でネイサンソン博士がアランを受け取ることになった。
アランは最初母親の腕の中で泣きわめいた。未知の恐怖が彼を支配したのだ。母親はなだめるように彼の頬を撫で、キスをして抱き抱えた。スタッフが母親の横からそっと手を添えた。
博士は「さあ、アラン怖がることはないよ。今から友だちを紹介するから」と笑いながら、水中で待っていた。博士がアランを抱き抱えると、アランは泣きわめいた。知らない人の触感と母親から引き離された孤独感、そして、水の冷たさのためだった。 赤ん坊が母親の胎内から出たときに泣くのはこういう気持ちかもしれないと思った。
アランは動かない手足を必死に動かして抵抗した。博士は、その大きな体でアランを優しく、しかし、しっかりと抱きしめていた。岸辺からは母親がアランに声援を送っていた。
今度は一頭のイルカが現れた。ここの面白いのは、イルカを人間が手配するのではなく、イルカの自主性に任せていることだった。だから、どのイルカが現れるのか、何頭が接するのかもイルカ任せだった。では、イルカが気分が乗らないときは、どうするのか? スタッフたちは、癒されることを必要としている人間が来たときに、イルカが来なかったことは今までに一度もなかったと答えてくれた。
現れたイルカは、例によってアランの周囲をゆっくりと周り始めていた。ネイサンソン博士によると、この周回は、人間の医者の触診と同じようなもので、水に放射される人間の波動(バイブレーション)で、その人間のどこが病んでいるのかがわかるのだと言う。それがエレンのように精神の障害であっても、水に放射されるエネルギーで敏感に読みとるのだと言った。
イルカがアランの身体にすり寄ってきた。先ほどのエレンの時には距離を持って近づいてきたのに、アランのときには、いきなり身体を寄せてきたのである。まるで、アランが目が見えなくて、触感が彼の主要な感覚手段であることを見抜いたかのようだった。アランは、その違和感に驚いて、さらに激しく泣きわめいた。それでもイルカはじっとしていた。身体をすり寄せたまま、動かなかった。博士も黙って待っていた。アランは泣き止まなかった。イルカはすっと身を引くと、また周回を始めた。泣きむずかる子どもをどうやってあやそうかと考える老医者のようだった。
今度は、イルカがアランのすぐ側でお腹を見せた。イルカがお腹を見せるのは、相手に危害を加えない安心の表意である。ネコでもイヌでも人にお腹を見せるときは、その人間を安心しきっている証拠だという。イルカも急所であるお腹をさらすことによって、相手の心を開こうとするのだろう。だが、目の見えないアラン少年に、それが伝わるのだろうか?
この世のすべては波動であると知っているぼくも、ともすれば「見えている」ことに囚われてしまう。「感じる」ことを大切にするのが、ヒーリングの基本である。イルカの行為は、波動である。その波動を視覚という感覚を持たないアラン少年は、普通の人以上に敏感に感じるはずだった。アラン少年がふいに泣き止んだ。そして、何かを捜すように手を伸ばしたのである。それまで、おろおろしていた母親が安心したようにイスに座った。
その変化は、岸辺で見ていたエレンにも伝わったようだった。彼女は黙って興味深げにその光景を見ていた。その表情には、何らかの意思が浮かび上がって来そうに感じられた。マーク少年も嬉しそうに笑っていた。
彼らは、ぼくのような見学者ではなく、当事者だった。自分がここに来ている理由を誰よりも理解していた。そのときである。ふと自分の足元に気配を感じたぼくは、そこに三頭のイルカが集まっていることを知った。
三頭ともお腹を見せてくれていた。一頭が「マアーッ」と鳴いた。そして、もう一頭がぼくの不自由な左足に鼻をすり寄せてくれたのである。ぼくは、自分の身体の障害のことをスタッフにも博士にも言っていなかった。なのに、イルカたちは知っていたのだ。「癒されるべきは、あなたもだよ」と言ってくれているように思えた。思わず胸が熱くなった。
イルカたちの優しさを一度でも知ったら、人はイルカに対しての認識を改めるという。クジラも同じである。人から聞いた話だが、以前、ある取材のボートがクジラの群に近づきすぎて、クジラたちがイワシを追い込んだ輪の中に紛れ込んでしまったことがあった。そのままだとボートは転覆し、危険だったらしい。ところが、一頭のクジラがすっと身を引いて輪から外れたのである。そこから逃げなさいと言うように。ボートを逃がすことは、自分たちの餌であるイワシの群も逃がすことだった。なのに、クジラは人を助ける方を選択したのである。
イルカやクジラの生きる権利を主張する人たちは、理解者たちの努力によって年々増えている。だが、彼らに対して、見せ物としてビジネスを優先する水族館関係者や一部の学者たちは、イルカはただのホニュウ類だと断定する。知能も擁護者たちが言うほどには高くないと。だが、 人間はイルカたちの知能指数を測る基準を持ってはいない。自閉症の子どもがこれまで表現する手段を持たないために、知能が低いと思われていたように、イルカたちの言葉や共感能力といった波動エネルギーが見えない人間には、イルカの真の知能は到底理解できない。人体のエネルギーを波動で見ることのできる科学者たちは、イルカの脳が中心から発達していると言う。それは、アボリジニの脳の発達形式と同じだと説明している。
ある宇宙的な意識体は、彼らこそ地球を代表する知性体であると言う。それは、人類が現れる四〇〇万年前よりもさらに一一〇〇万年もの前からの長い歴史を 持つイルカに対する正当な評価ではないかと思う。だから、ぼくは彼らを 「亜種霊長類」と呼んでいる。アメリカの人気SF映画『スタートレック』の 「故郷への長い旅」では、クジラの絶滅した二十三世紀の地球に、宇宙の彼方からクジラたちとの交信を求めてやってくる知性体が現れるというエピソードも描かれている。
人間がイルカたちについて本当のことを知るには、神話の世界から学んでいく必要があると思う。アトランティスやムーやレムリアの文明の初期には、ギリシヤ神話で伝えられるトリトン文明(トリテア人)の影響が隠されている。
人間はもっと謙虚になる必要がある。自分たちは宇宙の仕組みも生命の不思議もまだ何一つ本当には知り得ていないことを自覚すべきだと思う。大自然にひれ伏すような心を持てたとき、そこからすべての道が開けていく。それが、「祈り」である。