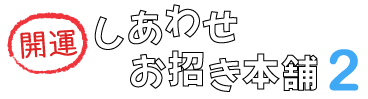お告げ – 番外編2
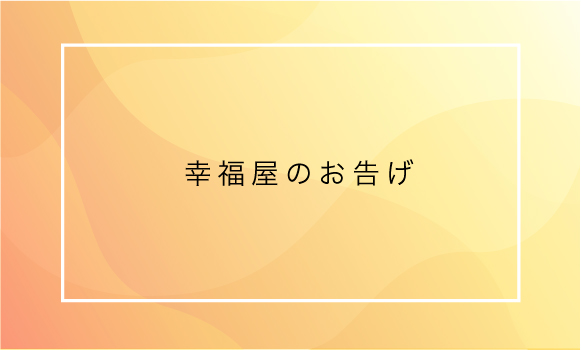
道の達人 本物は誰だ!
君の行く道は、果てしなくとおーい
本物の達人の極意
どこの世界にも、その道の達人はいる。だ が、本物はとても少ない。
昔、中国に、木の像を彫る名人がいた。そ の人の名は琳(リン)。彼の彫る虎は本物そっくりで、 生きているように見えた。鳥を彫らせれば、 いまにも飛び立ってしまうのではないかと思 わせる出来映えだった。人々は彼を「北の国 一の名人」と誉め称えたが、彼は自らを「東方不敗!大陸随一の彫物師」と自慢していた。
ある日、琳の耳に、像を彫る名人が南の国 にもいるという噂が入ってきた。その名人の 名は王(ワン)といった。王の彫った鳥は、美しい声 でさえずったという。琳はどちらが本当の名 人かを勝負したくなった。
やがて、時の皇帝が二人の名人の審判役を 引き受けることになった。鳥や獣、蝶など、 二人の彫った像は共に素晴らしかった。勝負 は何日も続き、五分と五分の引き分けに終わ りそうだった。
琳は焦った。自分こそ天下一の彫物師と人 々に言わせたかった。そこで、最後の勝負を 仏像で決めないかと提案した。実は彼には勝 算があった。彼の応援をしてくれる金持ちに 頼んで、金箔を思う存分使った仏像を作れる 自信があったのだ。
決着をつける勝負は、観音像を彫ることに 決められた。美しいだけでなく、人々がどち らを拝みたくなるかという一般審査も含まれ ていた。 琳は何人もの弟子を使い、贅沢に黄金を使 った。王はというと、彼は一人静かに滝に打 たれていた。審査員たちは、すでに琳の勝利 をささやき合っていた。
琳は、絢爛豪華な世にも美しい観音像を作 ることに成功した。表情も美しく、優雅で気 品があった。審査員たちも唸る出来栄えだっ た。それに引き換え、王の作った観音像は、 木彫りの素朴なものだった。
いよいよ審査の時になった。皇帝をはじめ、 一般の見物客がひしめいて見に来ていた。
まず、琳の観音像が公開された。人々の中 からどよめきが湧き起こった。光輝く観音像 がそこにあった。琳は自分の勝利を確信した。
王の番になった。だが、王の観音様は忽然 と消えているではないか! なんと、王の創っ た観音像は、天に昇って世の人々を救いに行 ったのである。
あなただけの「鉄人」になろう
本物と偽物はどう違うのだろう?
何から何までそっくりにまねてみせても、 偽物はやはり本物にはなれない。なぜなら、 本物とは形のことではないからだ。
人が何かを求めたとき、そこに道ができる。 あなたが歩いている人生も、じつはひとつの 道である。あなたは迷ってばかりいると思っ ているかもしれない。また、何にも考えない で生きてきたと思い込んでいるかもしれない。 自分の生に特別な意味などないと、あきらめ てしまっている人もいる。だが、それでもあ なたは道を歩いているのだ。
かつてのテレビ番組『料理の鉄人』に登場した人 たちは、和食の鉄人、中華の鉄人、そして、 フランス料理の鉄人というように、一般的だ からこそ評価されやすかったのである。たとえば、「今日はクラゲの塩焼きで勝負です。挑戦 者は、ムー大陸料理の第一人者!」という人 だったら、誰にも評価できないのだ。
あなたの人生は、人に評価されるためにあ るのではない。
ただひたすら昆虫が好きだった少年は、後 に歴史に名前が残るなんて夢にも思わなかっ たにちがいない。まして、ファーブル博物館 が建設されるなど……。
こんな言葉がある。
「世の中は、あなたが認めた分だけ、あな たに返ってくる」
あなたが自分の価値を自分で認めることが できるなら、誰に評価されなくても、あなた はそのときから成功者なのだ。反対に、どれ ほど世の中が称賛しても、幸せでない人はた くさんいる。人間、自分にだけは嘘はつけな い。あなたは、あなたの「本物」に成れれば いいのだ。
忘れないでほしい。人は、人に認められよ うと思った瞬間に、躓くのだ。
故マザーテレサは、ノーベル平和賞の受賞 のときにこう言った。
「すべての貧しい人の代表として、お受け します」
ノーベル賞も彼女には、最上の喜びではな かった。人の評価よりも天に喜ばれることの 素晴らしさを知っているからだ。
誰かに評価されなくても平気な人になろう。
天知る、地知る、我知る。それでいい。
ぼくは、それさえあれば十分にやって いけると思うのだ。
誰が自分を見ているかを気にして生きるの はもうやめよう。意に反して人に合わせて生きてきた人 は、どれほど社会的な地位や名誉があっても、 本物の自分の生を生きてはこなかったのだ。
道とは、本当の自分の人生である。
トイレ掃除道ひと筋四〇年という立花藤兵 衛さんにトイレ道の極意を語ってもらった。
「まあ、なんですわなあ、極意ちゅうもん やおまへんねんけどね、まあ、なんですわ、 私が四〇年間便所を掃除してきまして発見し ましたのは、人のはやっぱり“臭い!”ちゅうことで すかな」