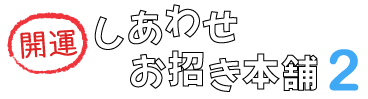お告げ – 35

半 身
昔、男と女は、一つだった。
一つの身体に、二つの心を合わせ持っていた。
二つの心は、まるで双子の兄弟のように仲が良く、いつも唄うように響きあった。
「やあ、あそこに美しい鳥がいるよ」
「ほんとね。羽が金色に光っているのね……」
「そうだ。今日は何を食べようか?」
「あたしの好きなモノ」
「それは、僕の好きなモノだね」
「そうよ」
二人は、同じモノを観て、同じように感じることができた。
大地を真っ赤に染めあげる美しい夕焼けを見て涙し、どこまでも透き通る海の蒼さに震えた。
寒い夜は、自分の腕で自分の身体を抱きしめた。互いにずっと抱き合ったまま、同じ夢を見た。
歩くのも一緒、考えることも一緒だった。宇宙の星を眺めて、流れ星に想う気持ちも一緒だった。
「どうか、私の愛する人がいつまでも幸せでありますように……」
そうして、二人は、とても幸せに生きていた。満ち足りていて、何の不安も不満もなかった。
星の運命が十二回まわり、世界に昼と夜が生まれた。
二人は、交代で眠るようになった。
男の方が昼起きていて、女は、夜になると目覚めた。
そのうち、二人は別々の夢を見るようになった。
それでも、初めの頃は、互いにその経験が新鮮で、見た夢を教えあった。
互いに起きている時間は、一日のほんの短い間になっていた。
いつの頃からか、二人はあまり話さなくなった。感じる心にずれのようなものが生まれてきたのもこの頃だった。
「風が気持ちいいね」
「そうね………………」
ある日のこと、水辺を散歩していたら、
二人の見ている前で、瑠璃色の花から虹色の妖精が生まれた。
妖精は双子だった。妖精たちは、青く輝く光の羽を広げると、別々の方向に飛び上がった。
二人は妖精を捕まえようと同時に手を伸ばした。
すると、ポンと蓮の花の咲くような音がして、二人は離れてしまった。
そのときから、男と女は、別々の人間になった。
……次の瞬間、二人は荒野に吹き荒れる風の音を自分の心の中に聞いていた。
紀元前に栄えた、イースター島ロンゴロンゴ王国のル・ケチャ族に伝わる創世神話である。
「………………」
バラ色の、いえ、真っ赤なウソです。たった今、創りました。もうしません!
私たちは、どうしようもなく異性を求める。
求めることで、時に、苦しんだり、喜んだりする。
一人の方が気楽でいいと頭では分かっていても、わざわざ困難を求めるかのように、異性を求めてしまう。
それは、きっと、遠い遠い記憶の中で失った「半身」を無意識に求めているのかも知れない。
この世のどこかに、自分から分かれていった半身がいる! 人は、そうして彷徨(さまよ)ってきたのではないか?
あるときは、何億年という生まれ変わりの旅をしながら。
白い勾玉と黒い勾玉で象徴されるタオ(太極)の図は、バランスを意味している。上下の三角形が組み合わさったタビデの星も同じ。
陰と陽、精神と物質、心と身体、闇と光、水と火、やさしさと厳しさ、東洋と西洋、過去生と人種、月と太陽……そして、女と男。
そのバランスは、ヤジロベーのように傾くこともある。恋愛や結婚(文明の交易もそう)が、本来幸せなモノのはずなのに、かえって傷つく人たちがいる。
いったい、何のために?
最初の男女が、世界中に増えていったのなら、最初のDNA(遺伝子)もまた、地球に拡がっていったのにちがいない。
記憶のカケラを辿りながら、男は女を、女は男を捜し求める。
恋愛したり、結婚をすると、二人の顔や雰囲気が何故か似てくるのは、分かれた魂が一つに戻ろうとするせいなのかもしれない。
そして、親が子どもに、無償の愛を提供できるのも、子どもという存在が、二人の魂の「結晶」だからだ。
それでも、この世界に意味のないことは起こらない。
二つに分かれた意味も、互いに「孤独」という栄養の真価を確かめ、自己を磨き、再び巡り会ったときに、驚くべき「進化」の鍵となるのではないか? そう思う。
そうして、私たちは、今日も、孤独の中で、愛を叫ぶのだ!
最後に幸福屋から一言。
大阪人は、なんで大阪人同志でくっつき合うんやろ? ただでさえ、血が濃いのに……。