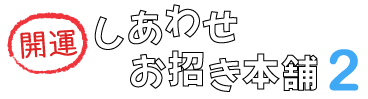お告げ – 34
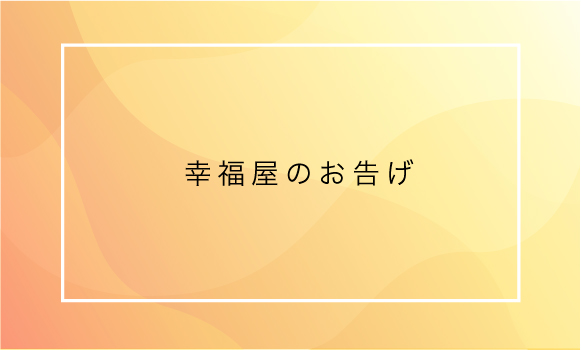
真夜中の二人三脚
(映画『真夜中の弥次さん喜多さん』というタイトルから思いついたので……)
「カンパネルラ! ボクたちはどこまでも一緒だよね!」
ジョバンニは列車の中で突然叫びだした。親友のカンパネルラが、急にどこか遠くに行ってしまうような気がして……。
「…………」
カンパネルラは黙って、澄んだ大きな瞳でじっとジョパンニを見つめていた。
おりしも、銀河鉄道は銀河の石炭袋(ブラックホール)へとさしかかっていた時だった。
そして、ふっと風が移るようにカンパネルラはいなくなった。ジョパンニが、ほんの少しよそ見をしていた間に。
「……ごめんね、ジョパンニ」
銀河鉄道999で、ロシアンハットをかぶったメーテルがテツローにお別れを言う感動的な場面である。
いや、ウソこきました! 宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の、カンパネルラが独り天に帰っていくシーンです(原文通りではありません)。
ワシは、このシーンを見るのがツライ。思わず感涙する。だが、ツライのに、何度も読み返したり、ビデオ(アニメの『銀河鉄道の夜』の方。漫画家ますむらひろしさんの主人公がネコの姿のもの)も何度も見てしまう。なぜか? なぜなの? なんなんニャ?(ロケット団か)
「帰る人より、残る人の方が辛い」という言葉がある。
旅先で、燃えるような、それでいて通りすがりのような恋をして、別れを迎える時、残された人は終わりのない顔になる。ボクは、なんだかズルイと思う。思い出のつまった場面に独り残すなんて。出ていく方は、新たなる世界が待っているのに。
けれど、本当は行く方だってツライのだ。なぜなら、「一緒に行こうね」と願っていたのは、他ならぬ別れを告げた人の方だったりするから。
人間はいつも独りで生まれてきて、独りで死んでいく。
そして、「お伊勢参り」の旅のように人生を渡っていく。
途中、共に珍道中をする相方に恵まれたりすると、人生に深みが増していく。
でも、それでも、いつかはまた独りになる。
そして、独りで天に帰っていく。
と、ここまで読むと、「今回は死生観の話か?」と思うだろう。だが、素直じゃないボクちんは、期待に応えてはあげないのだ。今回は、じつは「恋愛」の話なのだよ。
「……終わったな」と、『うる★やつら』のラムちゃんに恋するメガネのように、ジョニー・チップはつぶやいた。
何度目かの恋だった。
どちらが悪いのでもない。意識的に「オレは変わりたい! 変わらなきゃならないんだ」と願っていた人間と「変わりたくない。何も変えたくないの!」と変化を拒否していた人間がたまたま交わり(これは、魂と魂が出逢うからタマタマと云うのだ。おおっ、そういえばアマゾンの樹海にはマタマタという亀が……)恋にまで発展した後の当然の帰結だった。
ジョニー・チップはいつも何かに焦っていたようだった。「このまま何も起こらずに終わってしまうのか?」では、何のために? と、自らに問い続けていた。
アン・メレンデスの方は、自分が変わることで、自分の居場所を永久に失ってしまうのではないかと不安に脅えていた。だから、変わりたくなかった。何も変えたくなかった。もし、変わるならば、変わらなければならないのなら、周囲の環境が変わって自分の居場所を誰かが確保してくれてから、変わりたかった。
けれども、それは、走るスピードの違う二人三脚の走者が、自分のペースを主張しあうようなもので、いつか、足がもつれて転んでしまう、誰にも予想された恋だった。そして、自分たち自身もそのことをどこかで予感していた。
……ときおり思う。
恋愛とは、「二人三脚」で走るレースに似ている、と。
それが、結婚にまで発展したとしても、そこでレースは終わらない。本人が自覚しても、しなくても、レースは続いていく。
けれど、そのことを「自覚」している人たちがどれほどいるだろう?
人は、変わる。変わっていく。自分自身がたとえ「変化」を拒否していても、周囲の環境の変化(本当はそれさえも自分や周りの人間の複合的な想念で変化したんだけどネ)から、否応なく、あるいは順応して変わっていく。
人生というレースは、常に「変化」を要求するからだ。
それは、人間が「自ら進化する」ために生まれてきたせいだ。何かを変えることで、自分を殻に閉じこめていた「自分自身を愛から遠ざけるもの」を修正していけるからだ。
そして、そのことだけが、人間を宇宙とつないでいる「無限」に導く。
ただ、問題は、その変化が同じ方向に、同じ歩いていく道に進み、互いが寄り添っていけるかどうかである。
例えば、プラグマティズム(地位や所有物など物質的な栄光を喜ぶ)な傾向の自己チュー的な二人の男女がいる。その二人がふとした御縁から恋愛をしてしまう。多少、食べ物や趣味や好きなものが違っていても、「関心のあること」が互いに似た者同士だから、人生の「生き方」の意見がとても合う。
「オレってば肉が好きさ」
「あたいもあたいも!、肉食人種よん!」
「オレってさ、イギリスの新車が似合う家が好きだったりして、英国的ってか!」
「ウィイー、あたしもシルブ・プレ」(違うだろうが!)
と、二人はいろんな想いが一致していることを喜んでいく。そういえばなんだか顔や雰囲気も似ている。自分たちの親や兄弟よりも似ているかも知れない(想念が似ると、オーラが似てくる。結果、顔まで融合していく)。そんな二人がデートをしたり、旅行したり、互いに仕事や家庭の悩み事を話し合ったりして、関係を深めあっていく。まるで「この人に出逢うために生まれてきた」と思えるほど、運命的なものも感じていく。
ところが、ある雪の日、タケオ(誰?)は、一人のホームレスとの出逢いからボランティアに目覚めていく。夜の公園をボランティア仲間と一緒にパトロールしたり、海辺でオバさんたちと空き缶を拾い集めたり、火を囲んで自分の過去を告白しあうキャンプ・ファイアー(?)に参加したり。
そんな異種格闘技のような「交流」の日々が続いた。
いつしか彼は、今まで自分を支配していた「物欲」や「虚飾」の世界から遠ざかっていった。ブランドものの洋服や小物を追いかけていた自分がまるでウソのようだった。今では、ユニクロこそがブランドだった。鶴亀スーパーこそが、台所だった(なんのこっちゃ)。
だが、彼女の方は、変わってはいなかった。相変わらずバーゲン情報や海外旅行やセレブの事にしか関心がなかった。デートの時に、彼がボランティア活動の話をしても、遠い世界の話を聞いているようで、チョーダッサーイとか、つまらないと思うのだった。また、彼がいつのまにかベジタリアンになっていて、週に2回は通っていた焼き肉エステ「牛カク」(?)にも連れていってくれなくなったことに不満と寂しさも感じていた。最近では、彼の食生活は「微食」とかなんとかに進み、いずれは「不食人間」に変身して150歳まで若いままで生きるのだと、ワケの分からない事を口走る始末だった。
「あたしたちって、いつからスレ違いだしたの?」
と、いうように(えっ、ここまでが例え話かい!)、互いの変化のスピードが違いすぎたり、人生の関心事が移ろい、相手との接点が薄れていく場合もある。
そんなとき、二人の足を結んでいた「二人三脚の“赤い紐”」は、ほどけ始めているのだ。
そして、いつか別れが訪れる。
去っていく方は、「一緒に行けると思ったのに……」と心の中でつぶやき、残された方は、「いつも一緒だって言ったじゃない!」と叫ぶのだ。
それは、夫婦だって同じ。
結婚しているから、戸籍に入っているから、子どもがいるから、と、安心していると、相手は知らぬ間にエイリアンになっている。
余談だが、昔から「子は鎹(かすがい)」とよく言うが、それは、子どもがいなければ繋ぎ止められない夫婦の関係が多かったから、そう言ったのだよ明智君。
人は、たまたま出逢ったのではない。ちゃんと宇宙的な「ご縁」の中で出逢うのだ。たとえ、出逢いがよこしまな煩悩やワザとらしい合コンからだったとしても、その相手と出会い、恋愛することで、「自分ってどんな人?」を自覚し、起きていく「変化」を「進化」として変容させていくために計画されたものなのだ。
なぜなら、「恋愛」ほど人を変えるものはないからだ。
自分のためだけに生きてきた人間が、恋をすることで「相手の心を尊重する」生き方を学んだりする(それが学べない人もいるが。そんな人は別の形で学ぶようになる)。
この宇宙は、ラセンである。進化はラセン状に進んでいく。だから、課題を克服するために、何度も同じ経験をする。同じ事の繰り返しに見えるが、どんな人も確実に一歩ずつ昇って行くから(下っているように思えても昇っている。山道に上り下りがあるようなもの)、上がるにつれて見える景色は違ってくる。以前よりは、自分の弱点や相手の弱さに寛大になっていたりするのだ。
「二人三脚」の妙技は、さらに深い。
相手の事を思いやる心を育てる。相手のスピードに合わせて歩く事を学んだり、時には、じっと待ったりすることも学んでいく。
「人は、皆自分とは違う。相手に自分と同じものを要求するのも“自我”ではないか。みんな違っているから、それでいいんだ」と、学んでいく。「偏見」というタマネギの皮を剥くような作業の連続。もっとも、そう思えるとき、相手もまた同じ方向を見て進んでいるのだが(本人が気づかなくとも)。
ラセン状の宇宙の、DNAのような二重ラセンの故(ゆえ)である。陰と陽のなれそめか。
恋愛、それは、明かりのない暗闇の中を手探りで進む二人三脚なのかもしれない。
最後に幸福屋から一言(おおっ! 懐かしい)
出逢いと別れは、でんでん太鼓。さよなら三角、またきて四角。
「今の自分を超えること。繰り返し、超え続けること」
思えば、かなう! かな。