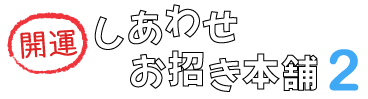お告げ – 29

前世の記憶Ⅱ
世の中には、自分にそっくりな人が三人はいるという。
もし、自分とそっくりの人に会ったら、どうするか?
私はイヤだ!
こんな人間は私だけでたくさんだからだ。
では、もし、そんな人間に出逢ったら……、
「決着をつけねばなるまい、だが、まだその時期ではない」と、言って逃げる。
前回、「前世の記憶」の最後の所で、大学の同窓会に呼ばれたことを告白した。そして、その話はまた、今度ね。と、書いたら、
「続きはどうなったんじゃい!」というお叱りのメールを幾つか頂いた。
「あれはね……、あれは、ほら、視聴率が低迷していて突然“打ち切り”になるテレビ番組があるでしょ。その最後に決まったように、“俺たちの旅はまだ終わっちゃいない”とか、“また逢える日を楽しみに”って、言うじゃない。あれと同んなじ軽いノリだったの。だから、ほんとは続きはないのよ」
と、誤魔化す気でいたのだが、生来の「アマノジャク」の性格は「前世」から引き継がれたのか、今回、パート2という形で告白してみたくなった。
さて、自分が忘れているのに、他人が自分の言動を異様に詳しく知っていることがある。
「おまえ、あのとき、こうだったよな」と言われても、ピンと来ない。「はて、そうだったっけ」と思い出そうとしても、思い出せないことはよくある。もっとも、「あなた、あのとき、私のことを好きじゃーと言ったわよね」というような、自分に都合の悪いことは覚えていても、忘れたふりをするしかないのだが。
今回は、自分が覚えていない「前世の記憶」を他人がよく覚えている、という困ったお話である。
たとえば、中島らもさんの『ビジネス・ナンセンス事典』(集英社文庫)には、「み-妙策」の項で、CFディレクターだったワシが登場する。その中で、ワシは缶コーヒーにタコヤキを入れるアイデアを企業に持ち込んで出入り禁止になった、という話になっている。けれど、そんな話は、らもさんにしたような、しなかったような、……曖昧として思いだせんのじゃ。あの夜の時か……。
当時のワシは、肩で風きって、「命がけの仕事しとるんかい、われ!」とクリエイターを絵に描いたような生き方をしとったから、そんな事もあったかもしれんが。
関大の同窓会(と言っても、同じ仏文科の人間が中心ではなく、たまたまフランス文学研究会-ワシは“ピノキオ”の歌のダニエル・ビダルに憧れてフランス人と結婚したいためだけに、仏文を選んだのよ-というつながりで、文学部、経済学部、商学部の人間が8人集まった)でも、私の知らない「私」がそこにいた。
ちょうど、「ほんに懐かしかー」と、変わり果てた関大のキャンパスをオヤジばかり(集まった8人のうち、7人までが独身。一度も結婚していないのが6人。類は友を呼ぶと言うが)で歩いていた時だった。
グラウンドにさしかかると、友人の一人が言った。
「ここや、ここ。加納君が、空手着を着て、野球をしてて、「仏滅!」と叫んでバットを振ってたんよ」
「せやせや、あれはキョーレツやったなあ。あのときが加納君を初めて見た時なんよ」
「あのときから、アホやったもんなあ」
と、友人達が口々に言う。
「……えっ?」
私は、遠い目になっていたに違いない。
空手着を着て野球? 「仏滅」と叫びながら、バットを振る?
それ、誰?
げ、現在の物静かなワシからは到底考えられん。
そうじゃ、きっと、みんなでワシを陥れようと企んだのにちがいなか!
途方に暮れるワシに友人の一人が追い打ちをかけた。
「ほんなら、モノホシザオで窓ガラス叩いたのん、覚えるとか?」
「えっ? モノホシザオで窓?」
怪訝そうに振り向くワシ。
「ほら、午前中の授業に遅れるから言うて、加納君、ぼくの住んでいた寮の二階の窓ガラスを人の家のモノホシザオ持ってきて、ゴンゴン叩いて起こしてくれたやん」
「そ、そうだったっけ?」
「ほんまや、寝てたら、窓ガラスにぬーっと棒が伸びてきて、ゴンゴンたたくから、初めはびっくりしたんやけど。お蔭で起きれたし……」
……ワシって、ええ奴やったんや……。
人間は、「忘れる」生き物である。
イヤなことを記憶から消し去ることで、心を守ったりする。
そして、結果的に「同じ過ち」を犯す。
忘れないでいられれば、同じ轍を踏まなくても良いのに、と思うが、なかなかそうはいかないらしい。
前世の記憶も、「思い出せない」から、平気で生きていられたりする。
ときおり、人が自分とそっくりの人間を見て、ぞっとするのは、もしかしたら、「忘れたい」記憶の断片を垣間見るためかもしれない。