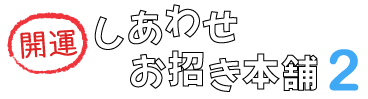お告げ – 24
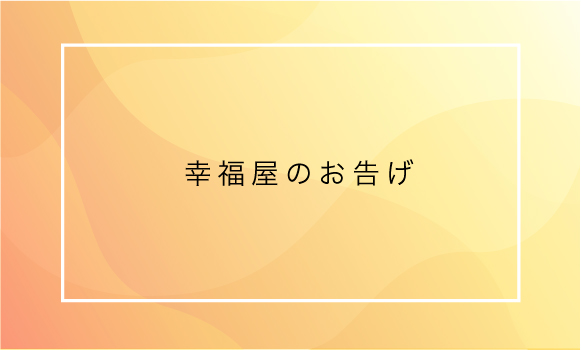
オタクの魂
『コジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』を観てきた。
友人の原坂君が、「モスラの声な、昔と同んなじやねんで」と、のたまうので観てきたのだが、正直、何でモスラが親子で出る必要があるのかわからなかった。が、作品としては、なかなかに面白かったのではないかと用心しながら思う。
なぜ、用心しながらかと言うと、うっかり「おもしろかった!」と言うと、「ええっ!、あれが?」と、冷ややかなエネルギーが来るからだ。
かつて、「コロッサス」という怪獣大好きグループを組織していた私としては、見識が衰えたかという視線は耐え難い。
怪獣映画をどの視点で評価するかは、意見の分かれるところだ。新ガメラシリーズを誉める人もいれば、昔の大映の「ほのぼのガメラシリーズ(ガメラ対ギャオス以降)」の方が安心して観られたという人もいる。
特撮技術や造形技術、コンピュータグラフィックの進化で、怪獣ものもよりリアルに、より社会への問題提起を持つようになった。また、かつての怪獣ファンがみんな大人になってしまったために、その層を満足させるための「オタク度」も比例して高くなった。
今や、私の高校生の頃とは違い、会社の部長の机の上に、カネゴンや怪獣ブースカがちょこなんと乗っている時代である。
ただ一つ、今のゴジラシリーズで疑問に思うことがある(いい年をして、何を真剣に)。
それは、弊映が、「とっとこハム太郎シリーズ」であることだ。
ハム太郎は前にも言ったが、意外におもしろい。思わず、涙してしまったこともある。だが、「怖いゴジラ」との弊映はどうかと思う。
別に、小さな子供たちであふれる映画館で、奇異の目で見られる居心地の悪さから言うのではない。また、ゴジラが終わったら、逃げるように席を発つ、大きな紙袋をさげた中年のオヤジと目が合って、互いにおもわず暗黙の会釈を交わしてしまうからでも、もちろんない。
昔と違って、リアルな怪獣の造形は、ホラー映画に近いものがある。ハム太郎を観に来た幼い子どもたちに“トラウマ”を作る恐れがあるからだ。
私が小学校の頃は、『ゴジラ、エビラ、モスラ 南海の大決闘』は、夏木陽介の『これが青春だ!』と弊映だった(えっ!、それは田舎だけだって!)。
関係者の方々よ。できれば、怪獣映画との抱き合わせは、幼い子どもの視線でよ~く考えてほしい。
子どもの柔らかい心が、破壊的なエネルギーの洗礼で、これ以上、傷つきませんように。
気の小さなオタクの人たちが、安心して観に行けますように……。
最後に幸福屋から一言。
『とっとこハム太郎』が終わって、ゴジラの最初のシーンを観て、「ねえ、帰ろ、帰ろ」とお父さんを引っ張った小さな女の子がいた。
お父さんは、後ろ髪を引かれる思いで、劇場を後にしたことだろう。
怪獣ファンの明日はどっちだ!