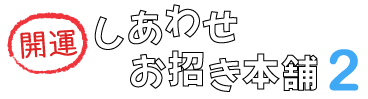お告げ – 16

さよなら三角、またきて、デジャ・ブーⅡ
子どものころ、コロッケをよく食べた。
一個、五円。中身には、肉なんかほとんど入っていなくて、すりつぶしたジャガイモだけ。
けれども、最高の御馳走だった、……ような気がする今日このごろ。
当時、下町には、こんな歌が流行っていた。
「♪今日もコ~ロッケ、明日もコ~ロッケ、そのまた明日も……♪」
毎日毎日、晩のおかずはコロッケだけ。スキヤキなんかは、一年に数えるほどだった。つまり、それだけ、コロッケは、庶民の味方だったのである。
親にもらった五円玉を握りしめて、肉屋さんに 走っていった幼い日々。 コロッケの、あの揚げた油の匂い、口の中を半分火傷をしながら、はふはふとほおばった時の口中に拡がる、なんともいえない甘み。
時に、ソースをたっぷりとかけ、時に、千切りキャベツとからませながら、ご飯のおかずとして楽しんだ夕げ。
その楽しく、せつなく、つましい記憶が、ときおり私を襲う。
だが、なかなか当時の味には巡り会えない。
デパートで売られている一個160円ほどの、昔から考えれば、“お大臣”のようなコロッケは、なんだか上品すぎて、しっくりこない。
中身もジャガイモだけでなく、野菜や上等の牛肉が入って、きっと油なんかも格段に上質なのだろうが、昔の方がおいしかったような気がするのである。
ああ、安モノの味が恋しい。あの香ばしいコロッケはどこへ行った……。
そうして、私の記憶は、町を彷徨うのだ。
だが、その記憶のお陰で、何度もヒドイ目にも遭ってきたことを告白せねばなるまい。
湘南海岸の某商店街に、某肉屋さんがある。
そこを通ったとき、ガラスケースに入れられたコロッケが目に飛び込んできた。 看板には、「揚げたて、一個100円!」と、ある。
と、私の記憶が、突如うごめき出した。
口の中には、あの香ばしい油と衣の香りが突然拡がる。
当然、その誘惑には何人もあらがえない。
私は、勢いよく、100円を差し出して、コロッケを買った。
「一つですね」という声と共に、店員が紙に包んでくれた。
だが、手渡された瞬間、手の中に冷えたコロッケの感触があった。
『どこが揚げたてやねん……』
頭の片隅に、何か不吉なものが走る。
そして、かぶりついた時、口の中には古くなった油の、後味の悪い、しつこい感じがひろがった。
その瞬間、私の中にある記憶が甦った。
前にも、この店のコロッケを買ったことを思い出しのだ。
その時も、冷えたコロッケの、油臭い、後味の悪さを後悔と共に噛みしめたことを!
そして、さらに、デジャ・ブーのように同じ思いを何度もしてきたことを!
……つまり、私は、何度も、その店で冷えたコロッケを買っては、苦い思い出を悪夢のように思い出していた、のである。
ドイツの某哲学者は、「人は、いつもラクな方に向かいたがる」と言った。
それは、「痛み」を薄れさせる脳内モルヒネ、エンドルフィンの働きにも似ている。
私もイヤな思い出よりは、楽しかった思い出を無意識のうちに追い求めているにちがいない。
私の記憶の中で、神聖なコロッケの香りとおいしさの記憶が優先され、苦い記憶が封印されたまま、あの肉屋のコロッケを何度も買ってしまうのだ。
そうして、悲劇は繰り返される。食べる度に、禁断の封印が解かれるのだ。
さて、あなたの記憶はどうだろう?
最後に、幸福屋から一言。
具の少ないラーメンと肉の入っていないコロッケは、人を下座の心にさせる。