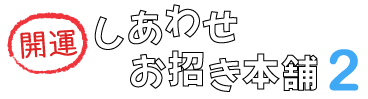風の言葉 – 25
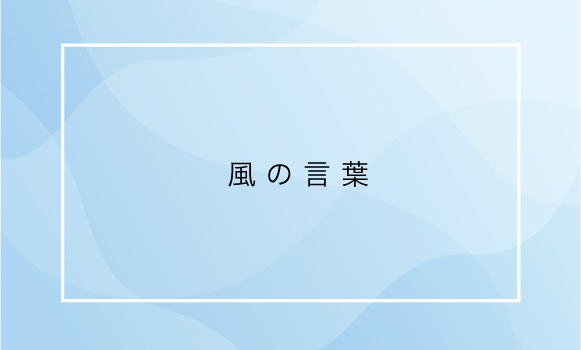
幸せになるための条件
……喜びの後ろに、悲しみがいる。涙の隣に、笑顔がある……神さまの造った小さな人たち……。
昔、みつはしちかこさんの 「チッチとサリー」の中に、そんな言葉が書かれてありました。
きっと、多くの人は、今も、「幸せ」になるためには、何かの「条件」がいる、とか、「何かを得ようと思ったら、何かを犠牲にしなくちゃいけない」と思っているのではないですか?
あるいは、良いことがあったら、悪いことも起きる。悲しいことがあっても、嬉しいこともある。人生はプラス・マイナスだと。
かく言う私もそう思っていた一人でした。
人は、多くを望んではいけないのよね、と。それは、きっと、多く=欲だと思ってきたから、でしょうね。
しかし、私たちは、多くを望まないでも、“すでに与えられてきた”ことに気づかなかっただけなのかもしれません。
それが自覚できない、あるいは、見えないから、「もっと、もっと……」と欲に変化していったのでしょうね。
そうして、自らを「持たないように」、「望まないように」と戒め、与えられた恵みに目もくれず、自分に条件を課してきたのだとしたら。
「清貧」という言葉も、そんなとんでもない誤解から生まれた言葉のように思います。
……確かに、「天は二物を与えず」という言葉はありますよ。
けれども、「天は二物も三物も与えた」という言葉も聞きますよね。
美貌も才能も何もかも恵まれているように見える、そんな人は案外、結構います。
それを「不公平だわ、ブー!」と嘆くよりも、「じゃあ、私にも」と望んだ方がいいのだと思うのです。
だって、神さまは、ケチな存在ではなく、すべてを与えてくれているのですから。
人間が、自分で自分の「得るモノ」を限定してきただけ。
「これとこれをもらったら、とてもこれまではもらえないだろう」とか、「きっと、こんなに望んだら、バチが当たる」と。
神さまはバチなんか当てませんよ。人間が自己処罰してきただけですから。
仏教の法華経に「放蕩息子」の喩え話があります。
ある長者の家の門の前に、浮浪者のようにボロを身にまとった若者が座っていました。
長者は一目見て、それがずっと昔に家を出て行った我が子だと知るのですが、若者の方は、そんな過去をすっかり忘れてしまい、こんな立派な家の前に座っていたら、いつ怒鳴られるかと恐れていたのです。それでも、何か恵んでもらえればありがたいなと思いながら。
長者は、番頭さんを呼んで言いました。
「あの門の所に若者がいるな」
番頭も気づいていたと見えて、眉間にシワを寄せて答えました。
「はい、おります。商売の邪魔ですね。追っ払いましょうか?」
番頭の剣幕に、長者は慌てて言いました。
「いや、じつはあれは私の子なのだ。本人も気がついていないだろうが……」
驚いたのは、番頭さんの方です。
「ええっ! では、すぐにお迎えに参ります」
長者は手で制して、
「いやいや、いきなりそんなことをすれば逃げ出してしまうだろうよ。何か悪いことでもしたかとな。だから、番頭さん、あの若者の所に行って、何か仕事を与えてはくれないか? そして、その仕事ぶりを見て、少しずつ給金を上げてやってほしいのじゃよ。それで、仕事を覚え、身なりも整って、ある程度、自覚が出てきたら、初めて、親子であると名乗ろうと思う」
……そうして、若者は、長者の家で働くことになり、やがて親子としての再会を果たすのですが……。
聖書にも同じような喩え話がありますね。やはり、ボロを身にまとった若者が王宮の前で倒れ、その者は王の後継者たる指輪を知らずにはめていた、というお話ですが。
まるで人間は、自分で自分を許しながらでないと、幸せになってはいけないと決めてしまっているかのようですね。
最初から、すべてを与えられているのに……。
何の条件を満たさなくとも、すでに「幸せになる権利」を有し、そのまま成ることが許されてきたのに……。
自分自身に条件や段階を求めるから、きっと、人にも条件や段階を求めてしまうのでしょうね。
肩書き(条件)社会や学歴社会が生まれたのは、そんな深い自己限定(コンプレックス)からかもしれません。
何かを我慢したり、犠牲にしたり……、そうして、初めて、何かを得ることが許されるのだとしたら、この世界はいつまでたっても、どこまでいっても、悲しみと隣り合わせの喜びしか得られないでしょう。
それでは、宇宙は何の為に、人にすべてを与えたのか? 進化とは、いったい何だと思っているのでしょうね?
もし、「進化」を単純に“人より優れること”とか、“今の自分を超えること”と思っていては、今のたくさんの不幸を作ってきた「競争社会」の中で、もがいてしまうだけです。
進化には、条件など必要ないのです。
自分で作ってきた「制限」や「自縛=フィールド」を自ら外して、誰もが直接に神(宇宙と言い換えても可)と繋がっていくことだけで良いのに……。
それが、「意識の自立」を果たした、ということなのだから。
2008年3月26日 桜が咲いてきましたね。うーん、いよいよ、お花見の季節かあ……。みんなで手弁当を持ち寄って、美味しいタマゴ焼きなんかをちょっとずつつまんで、純米酒をくいっと飲んで、お猪口で落ちてくる花びらをそっと受け止めたりして……。わいわい、がやがやと世界征服の話しでもするといいなあ……。