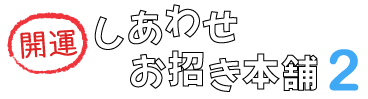風の言葉 – 37
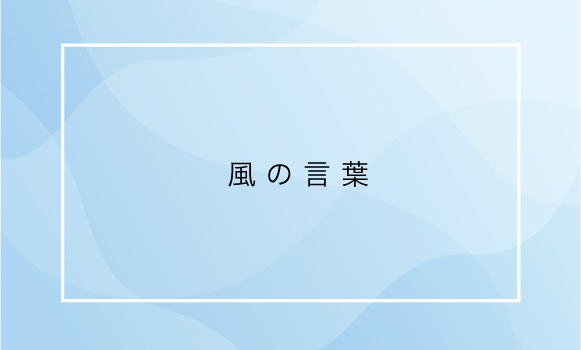
まんじゅう怖い
人は何を、どうして恐れるのだろう?
……あれほど怖い、怖いと言っていた饅頭を旨そうに食べている熊五郎を見て、長屋の連中が怒って聞いた。
「おい、おまえは本当は何が怖いんだ!」
すると、最後の饅頭をペロリと平らげた熊五郎が言った。
「今度は、苦い茶が怖い」
有名な落語「まんじゅう怖い(別名 好きと怖い)」のオチです。
人間って、いろいろな「恐れ」に縛られていますよね。
中でも、自分が信じてきた“世界”が崩れてしまうのが一番恐ろしい。
だから、サスペンスものでも、一番怪しくない、誰よりも自分に親切だった人が、真犯人だとわかった時に恐怖するのですね。
日常に、“非日常”が入り込んだ場合などもそうです。
昔、有名なCMディレクターの川崎徹さんが、「テレビを通した“現実”を人は受け入れる」、と語りました。
例えば、殺人事件が自分の住んでいるマンションで起きたら、大ショックでしょう。もう、怖くて、その日から出かけるときも鍵をかけたのかと何度も確認しなければならなくなったりします。ところが、その事件をテレビを通して知ると、意外と受け入れてしまうのです。話題の事件のマンションに自分がいる、まるで、ドラマのよう、と。それは、テレビが非日常を日常に変えてしまうからでしょうか?
ある意味、感性のマヒのように私には思えるのですが。
また、予言をする人がいて、近くの公園で「もうすぐこんな事があるぞー」と叫んでいると、おばさん達は「何アレ? 変な人コワーイ」となるのに、テレビで街角の奇人として公園で叫んでいる処が映ると、有名人のように錯覚してサインをもらいにいったりしてしまう。
テレビの力なのか、自分の現実にはないものを受け入れられない感覚というか……、それが、「変化を恐れる」ということのように思います。
先日も(2008年10月18日)、京都のボディライトニングのスクーリングの当日に、新大阪の駅で階段から落ちて、右足を何カ所か複雑骨折してしまった時のことでした。電車の中で、乗り合わせたおばさんが心配してくれて、「大丈夫ですか?」と聞いてきてくれたのです。痛そうにしていましたから。
幸い、ボディライトニングの講師の人たちが何人も一緒の車両にいて、折れた足首の骨の“入れ替え(ボディライトニングには、本人の身体から内蔵や骨等のデータを引き出して、移し替える技があるのです)”をしてくれました。その電車に乗るまで、足先が変な方向に曲がっていたのですが。
それで、私が「ありがとうございます。でも、大丈夫です。足首を複雑骨折したのですが、たった今、修復して取り替えましたから」と言った途端、顔をプイと背けてそのまま狸寝入りをしてしまいました。
きっと、骨折した足を目の前で修復するなんて、どこかの怪しい集団か、秘密結社の人たちかと思ったのでしょうね。
でも、もし、ボディライトニングの技が、テレビの“みのもんたの番組”で紹介されていて、それを見ていた人だったら、「それで、どうなったのですか?」と興味津々で聞いてこられたのだと思います。
まあ、ピラミッド型の情報伝達でしょうか。どんな突拍子もないことでも、一番下の方まで情報が行き着くと、“非日常”でも“普通”になったりします。
本当は知らないのに、“知ったつもり”になれるから……かな。
以前、知り合いにダイエットの話を聞かれた時も、「微食の勧め」や「水をたくさん飲むこと」までは受け入れてくれたのですが、「栄養って、無理に摂らなくても大丈夫なんだよ」と言った途端、警戒心で耳を閉ざしてしまったことがあります。
もしかして、一日30品目の野菜とかを忠実に守っていた方だったのでしょうか?
人間は、自分の知らない事に出逢うと、たいていは「拒否反応」を示します。
それは、やはり「恐れ」なのですね。
例えば、肌の色や人種の違い、それらも“互いによく知らない”から、「恐れ」に変化するのです。
けれども時折、「恐れ」を超える“好奇心”や“愛”のある人がたまに現れて……、そういう人が、時代を進化させてきたのです。
だから、「知る」って大切なのですね。『知ることは、力なり』と申します。
ほら、『幽霊の正体見たり、枯れ緒花』って言うでしょう。
ならば、「知らせるように努める」ことは、“愛”でしょうか……。
2008年11月12日 今日は朝から冷たい雨が降ったりして、洗濯モノが乾きませんでした。そうそう、お昼にカレー焼きそば作って、ビールで楽しみました。メッサ美味しかったです。『ヒミコ伝』も一般の方に浸透するのは時間がかかりますが、多くの方の理解と共感と「メチャメチャ、面白かったでー(なんで大阪弁?)」という応援のお蔭で、少しずつですが広まっています!(ような気がします)