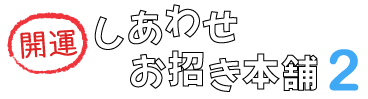お告げ – 33
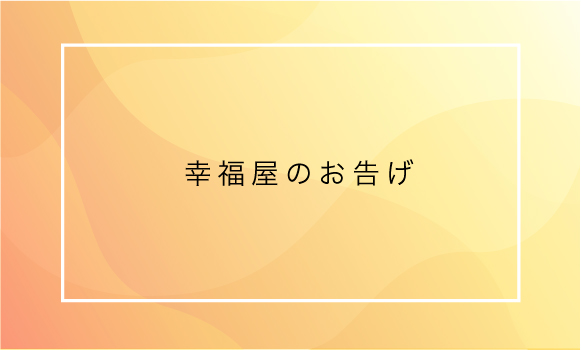
微食のシンクロニシティ
シンクロニシティ(共時性)は、時に、自分自身を思いもよらぬ方向に引っ張っていく……。
前回、5月4日に更新した、この「幸福屋から、一言」(そう言えば、最近、最後のキメの一言、……言うてへんような)でワシ自身の「微食」について告白した次の日、5月5日の夜8時から放映されたフジテレビの『奇跡体験! アンビリーバボー』という番組を何気なく見ていて驚いた。
なんと、「アンピリバボーな食生活」というタイトル(番組の内容はこのページに出ていますので、参照してください http://www.fujitv.co.jp/unb/ )で、「不食」の事が放送されているではないか! 離乳食の頃からジャムパンだけで生きているという、イギリス・サフォークス州ストウマーケットに住む15歳の少年、クレイグ・フラットマン君のことや、もう5年間も食事もしない、水さえも飲んでいないという、ロシア南部、黒海沿岸のクラスノダルに住む女性ジナイダ・バラノワ さん(68歳)のことが紹介されていたのだ。さらに、同番組では、菜食主義でもビタミンB12が不足しないということにまで言及していた。ロシアのジナイダさんに至っては、植物の光合成のように「太陽の光を食べて生きている」というウルトラセブンのような体質までが証されていた。番組のナレーションも、「食べることは、身体の栄養補給にもなるが、同時に、活性酸素を生み出して毒素を作り、身体に害を為していく行為とも言える」と、実に、テレビでは言えないはずのことまでサラッとフォローしてくれていたのだ。
ワシは、番組を見ながら、そっと胸をなで下ろしていた。「あー良かった。ワシの方が先に書いといて……」と。
友だちも少なく、新聞も取っていないワシはそんな番組があることも知らんかった(もっとも、その番組を先週見ていたら、予告でそういった内容-ビタミンB12の話までは出ないと思うが-を知っていても不思議ではないが、屋久島のおサルさんに誓って、見てはいない!)。
この現象は、『不食』の著者、山田鷹夫さんの言われるように、「さまざまな所から、“食べないでも生きられる”と証明する人達が現れてくる」時が近づいてきたのだろうか……?
だが、一般の人の反応はどうか?
先日、久しぶり(屋久島から帰ってから、しばらく遠赤外線のような屋久島効果でボーッとしておりました。そう言えば、ワシは昔、いつもどこか遠くを見てポーッとしていた子どもじゃったので、近所の人から、「ポーの一族」と呼ばれておった)に弓のお稽古に行ったら、「この前、テレビでなんにも食べないで生きているって言うヘンな人が出ていたわ」とオバチャンたちが話していた。
「見た、見た。でも、ホントかなあ、あたし、ウソだと思うわ!」
「誰も見ていない所で、なんか食べていたりしてね」
オバチャンたちは、きっと苦労して取材したであろう番組を、何の根拠もなく「あたし、ウソだと思うわ」と断定して、言い捨ててしまう。
きっと、彼女たちの頭の中では、日常に「非日常」を持ち込ませてなるものか!、という種の防衛本能みたいなものが働いているのにちがいない(それが、自民党が長い間、日本の政権を独占してきた秘密だったりして)。
そして、「そう言えば、加納さんもまだ1食? それにしては元気よね」と、返答に困る疑問を投げかけてくれた。
そうなのだ! 一般のフツーの人は、「飛躍」を嫌う。自ら望んで「変化」をしたがらない。変化は、常に自分の目に見えない処で起こっていて、その流れに自然に巻き込まれていくことを願っている。だから、夕食は野菜ジュースだけのダイエットとか、「プチ断食」なら、「太ったら困る→水着が着れない→なんとかしなくっちゃ」と許容範囲の変化で納まるのだ。けれど、それがいきなり「不食」と聞くと、外界の刺激にクルっと丸まってしまうダンゴ虫やアルマジロのように、「あたし、聞こえない! あたし、認めない-スピード・ワゴンか?」となってしまうのである。それが、「あたし、ウソだと思うわ」の論法となる。
ワシが人に「微食」を薦めるのも、「人は段階を経てゆっくりと変化する」と感じているからだ。『こどもの大統領』(学研)でも、あの子は、いきなり「戦争反対」は難しいとからと考えて(いや、無意識か)、まず軍隊を別なモノに変えようとしたのではないか……。
ともあれ、ワシは逢う人ごとに、「微食」を薦めてきた。
仕事で出逢う人たちはもちろん、イタリア旅行で知り合った藤井進介さん(仮名)や杉本浩司さん(仮名)や今井光穂さん(仮名)や屋久島で出逢った森林フェチの鈴木宏紀さん(仮名)にも、「ワシがこんなに元気なのは、食べていないからじゃ!」と微食を薦めた。この前なんか、両国ですれ違った、おスモウさんにも薦めてしまった(ウソです。ゴメンサナイ)。
その甲斐あってか、少しずつ周りにも変化が現れてきた。メールで、「微食に賛成!」と言ってきてくれる人たちが増えてきた(ワシの他の本には賛同とは言ってくれないのに)。
あの「絶対過食」とも言うべき、ムーの編集長の土屋さん(仮名)までもが、一週間に一度のラマダン(イスラム教の信仰の中の節食の行)を行っているというではないか! その「変化の兆し」を伝え聞いて、ワシは、希望の灯を感ぜずにはいられない。
じつは何を隠そう。これこそがワシの最終目的の第一歩なのだ。
ワシは、ワシの「悲願」はなあ……、死んで、生き返ってまで、したかった事とはなあ……。
恋愛して、旅行して、おいしいもの食べて、一週間に死ぬほどアニメと怪獣もののテレビを観ること、そんなことでは断じてないのだ!
人類から、「戦争」と「飢餓」を無くすこと! なのですよ。
日本の食糧自給率は、実質35パーセントに満たない。
アメリカやフランスの自給率は、120パーセントを越え、他国に輸出できるほどである。10億人近い人口を包含する中国も、アメリカのマグドナルド戦略(牛肉の消費量を増やしたため、その飼料としての穀物が足りなくなった)が入ってくるまでは、自給率は90パーセントを越えていた。ドイツの自給率は100パーセント近くあり、日本と同じ島国のイギリスでさえ、80パーセントの自給率を誇っている。先進国、経済大国と言われる国の中で、日本だけが自国の国民を自分で養えない。しかも、外から入ってくる食糧には、ポストハーベストのような毒性の強い「農薬」がこれでもかと言うくらい、たっぷりとかけられている(日本の自給率を低くしたのは、誰だろうね? ワシ、知ってるけど)。
そのことをずっと前から危惧していた人たちがいる。九州で循環農法を指導して、「安全な食べ物」を供給し続けている赤峰勝人さんもその一人である。赤峰さんは、かねてから日本の食糧危機を訴えてこられた。そして、「百姓塾」を開催して、安全な農業を日本に取り戻そうと努力されている。
農業のシンクロニシティは、全国各地で共鳴しだした。そして、今、二宮のポンポコファームの中村ポン吉さん(仮名)など、多くの若者が安全な農業に携わり、食の生産に励みだしている。
けれども、その数は、消費にとても追いつかない。創っても作っても、「食べる」方が多いのだ。
もし、日本人のほとんどが朝・昼・晩の三食ではなく、1食に変えることができれば……。一週間に5食程度(一日に5食ではないよ、土屋さん!)の人が2割を越せば……。自給率は、当然の事ながら跳ね上がるのではないか?
「食べない」事で、「食べ物」に対しての「喜び」や「感謝」も生まれ、「一食」を大事にするのではないか。そして、他の生命まで、慈しんでいけるのでは……、と思うのだ。
人間は、「飢える」恐怖から、「戦争」を繰り返してきた、と言っても過言ではない。
他者を犠牲にしないで「生きられる」なら、戦争に働きかける「意識体」にも理性で「抵抗」できるのではないか?
小さな個人の「微食」。けれども、目に見えない変化が、いつも人知れず起きているように、いつしか、多くの人が「微食」に取り組むことによって、健康も幸せも取り戻せるようになる? そんな、「夢」を見てしまう、今日この頃のワシである。
【追 記】
作家になってから、真剣に就職したいと考えたことがあった。国連のWHOの一機関である「世界食糧機構」の日本の支部長(横浜ランドマークタワーにあります)の募集があり、履歴書を送って応募した。2次選考まで残ったけれど、最終的に何の連絡も来なくなった。「世界の子どもたちに食糧を供給する仕事」と夢見たけれど、きっと、ワシより相応しい人がその任に付いたのにちがいない。そう思ってあきらめた。しかし、後で、ある人から、「国連も政治ですから、本当にしたいことができないことの方が多いですよ」と聞いて、そうかもしれないと思った。ワシが「愛の光500」の運動を呼びかけ始めたのも、国家という「組織」を信じられないからだ。「人の温もり」のために必要な「変化」は、潮流のように、「草の根」的に拡がっていく事でしか起きないように思う。独り言だけど。